Ⅷ 盤渉調 『青海波』
邦楽の清元に同名の三味線音楽が有りますが(1.894.6.20初演)これと全く関係はあ りません。
雅楽では別名として、「静海波」「清海波」また「青海破」とも書かれた文献もあり、現 在『青海波』と統一されています。
青海とは中国西域の地名<チンハイ>のことで、その地方の風俗舞が長安に入って、舞 楽として完成し、三部形式の破の部分を残して「青海破」としたものです。
わが朝に伝わってから、題名の由来を見失って、自然風光の謂いから「破」が「波」に 替わってしまったものとも、言われています。
そして舞楽として渡来した当初は、平調だったようです。雅楽のうちでも、その装束 は最も華麗を極めたものとして知られていますが、演技を伴わない管弦楽曲として演奏 する場合は、仁明帝(834~51)のころ改定された盤渉調と設定されています。
以後左方の楽・複合二部形式曲として、律動の指定は<中曲・早八拍子>となってい ます。本講の課題は、その第一部のみとしましたので、その部分の構成式を示しておき ます。
盤渉調 青海波 構成式
それでは当課題楽曲部分、第一楽部の龍笛で使用される総音域譜表から、音列式を解 析し、内在する曲調の類推を試みることにしましょう。
[譜例・166]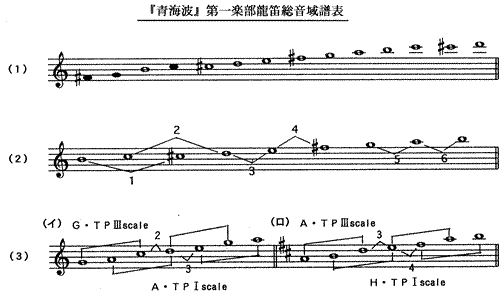
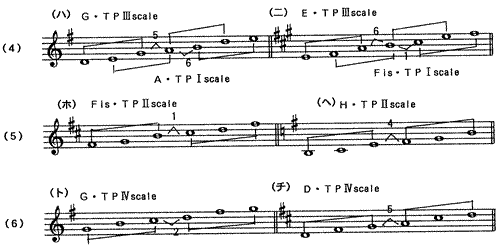
『青海波』第一楽部龍笛総音域譜表
譜例(166)の1段目の総音域譜表から、高音域旋律型楽曲で、しかもその高音域 に経過音的黒符頭が存在しないことは、上行跳躍型が主体となっていると言う、曲趣の 特徴が想像できます。
これを2段目に整理した音列式には旋律的長二度が6箇所あり、そこを依拠として、T Pを類推すれば、3段目の(イ)から6段目の(チ)に至るまで、合計12種類の曲調 の成立が見られました。
そしてこれらの曲調の中から、副題の調号の主調性は、(ロ)のH・TP�か(ヘ)の H・TP�かいづれかと見て、略々間違いないと思われます。
さらに本楽曲の沿革から、(ト)と(チ)のTP�は、先ず存在しないものと見てよい でしょう。
[譜例・167] 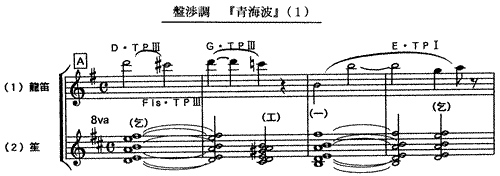
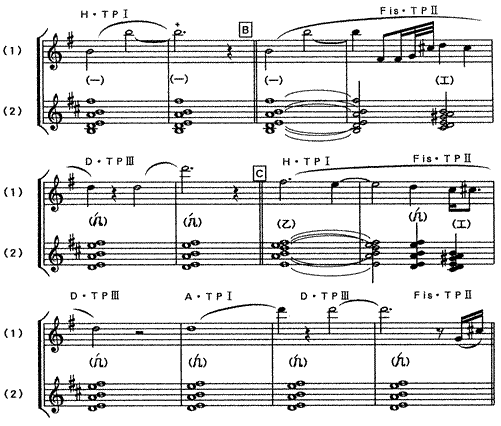
盤渉調 『青海波』(1)
[譜例・168] 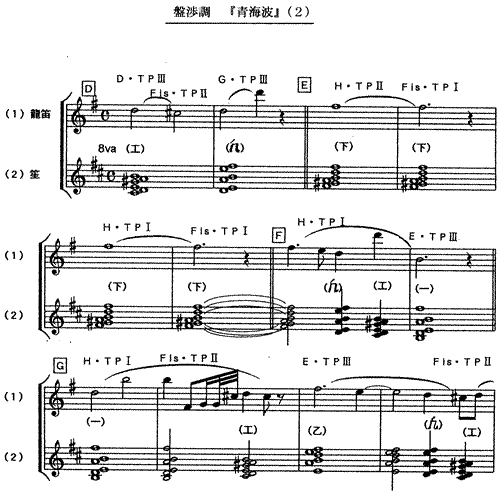
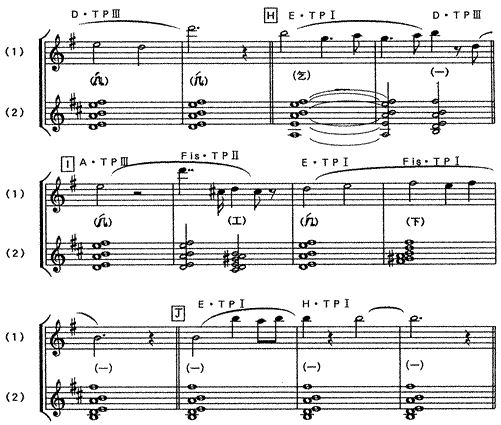
盤渉調 『青海波』(2)
譜例(168)は D 楽詞から G 大楽句までが挿入旋律部減楽段で、 H 楽詞 から J 小楽句までが副旋律部増楽節です。
面白いことに、前楽段の最終曲調を受けて始まる旋律に、対応する合竹エを用いられ ています。勿論ここは整合ですが、1Bの前半を凡、そして後半に初めてエとなってい れば、さらに評価の整合度が高いと思われますが、挿入旋律部とした位置づけに相応し く、前楽節の最終小節4拍目裏から上行する、装飾進行を受けて経過的密集多声エから 楽節の始まりとしたところに、意識的変化形が感じられ、その創意の跡が窺えるようで す。
果たせるかな副旋律部 H 楽詞以下 J 小楽句までを含んで、この2楽節内の合 竹エの五箇所は、総て理想的整合と言う評価が与えられます。合竹を中心に考えれば、本 盤渉調は経過的手移りのエの存在にあると、言って良いかとも思われる程です。
そして H 楽詞1Bから2B前半までの合竹乞は対応旋律音の時価が余りにも少な く、些かむりがあるのではないかとの、意見もあろうかとも思われますが、ここの旋律 部を良く見ると、mi (h") do (g") re(a") - do. re と言う、長二度3連続音 do - re - mi の中間音解決型で re の音に第2核音的支配機能のあることが、推測できます。 従って時価の多少に関係なく、その支配的音に対応させているところに、感覚的確かさ を感ずることが出来ます。従ってこの合竹の評価もまた、文句無しの整合でしょう。併 行多声の状況を無視すれば、その対応的意識は現代的立場から見てもまことに理に叶っ ていると言えましょう。
その他の合竹の評価には、取り立てての問題は無いと思われますので、各自でご検索 下さいますようにお願いしておきます。
最後に類推曲調について一言、説明を加えさせていただきたいと思います。それは
J 小楽句の曲調推移についてです。ここの2B3Bの終止曲調は、H・TP�でも 良いのではないか、と言うことです。それはその前の1Bの4拍目裏の re (a") から mi (h") に進んで、解決している終止形である故に、H・TP�と類推したわけで す。1BのE・TP�は動かすことの出来ない曲調です。この第2核音 a" は同時にE・TP�の下属調A・TP�の第1核音を共有しているところから、その併行陽音階 H・TP�に進むことが最も自然な推移と判断したわけです。〔譜例(166)の(ロ) を参照〕そしてこれは当然仮装終止形です。