Ⅴ 双調『酒胡子』
小曲早四拍子の『酒胡子』は本来下無調(Fis)として渡来した、演技を伴う雑楽と言 われていますが、唐楽から度羅楽か高麗楽か、その出所がはっきりしていません。
雅楽の六調子として統合された際、当課題の双調に改定されたようです。管弦記録総 譜の第一部には、壱越調のものもありますが、これは大分国風化の影響を受けて作調が なされています。最も其の古風を伝えているものは、矢張り原調に近い双調の楽曲でしょ う。楽式は前曲の『長慶子』同様、複合二部形式となっています。
双調『酒胡子』構成式
(複合二部形式)
同じ複合二部形式としても、構成式を見ると奏楽的様相にかなりの差異があります。
それでは上記課題楽曲部分の、龍笛の使用総音域譜表から、前例に従って曲調を予め 類推することにしましょう。
[譜例・154]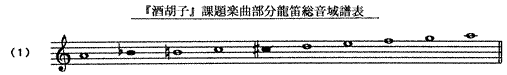
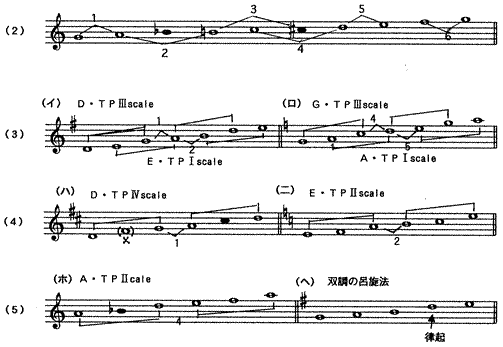
『酒胡子』課題楽曲部分龍笛総音域譜表
譜例(154)の2段目の、整理音列式の中の長二度部位ナンバー3からは、TPScale の成立は果たせません。つまりこの Ci s は、本質的経過音で、例えば装飾的打音のようなもので、音階機能には組み込まれないものと見るべきでしょう。敢えて音階機能音 の一つと見做す為には、4段目の(ハ)のD・TP�scale の露頭部分と見ることが出来ます。
しかしこの Scale の第一中間音Fi s は、楽曲中のどこにも出てきません。合竹の中の共有通奏音として、響いているだけです。従って一応は潜在的曲調として、(ハ)の 沖縄陰音階はキープしておくことにします。
ともあれ類推曲調としては、3段以下の(イ)から(ホ)までの五音階構造、合計7 種類となりましたが、無理をしている沖縄陰音階は、管弦楽曲では初めてのことですの で、少々気になる点もあります。そこで参考までに、本楽曲に入る前の双調の〔音取」を 検討してみることにします。
[譜例・156]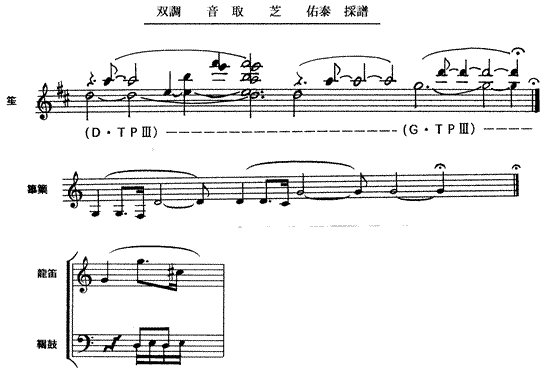
双調 音 取 芝 佑泰 採譜
この譜例(156)は、芝 佑泰氏の採譜によるもので、笙譜の下部の括弧内の曲調 は、筆者の類推曲調を記入したものです。
そしてこの楽節譜の曲態は、自由テンポ( Senzza Tempo)です。笙の音頭のソロ8呼間、つまり9拍目あたりから篳篥が加わって、そっと律動感を探って進み、最終音の フェルマーターのところで、意気を揃えると言う、極めて恣意な曲趣を望んだ技法の処 から、この様な記譜様式となったものでしょう。
さらに終音フェルマーターと同時に、龍笛と鞨鼓がブリッジフレーズとして加わって、 おもむろに本楽曲に入るわけですが、この龍笛のブリッジに、なんとCi s が導入音的に用いられています。主音のGから減五度下降跳躍しています。この減五度は度羅楽と か、中国古代の俗楽胡曲に出て来る、南方系の慣例律です。となると本曲の題名の動機 は、「酒に酔った胡国(外国)の人」と言うことでしょうか。これにはなんの文献的証拠 がありません、飽くまで筆者の仮説です。
しかしそれにしても、音取りを検討したことは、決して徒労ではなかったと言って良 いでしょう。笙の合竹の曲調は、D・TP�とG・TP�で構成されていることが分っ たこと、そして潜在曲調の(ハ)のD・TP�は、確かに存在していたと言うことです。
[譜例・157]
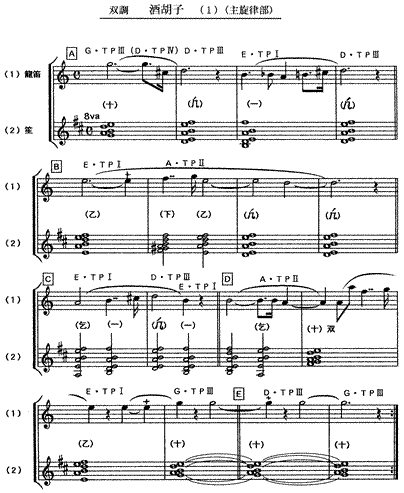
双調 酒胡子 (1)(主旋律部)
譜例(157)は、第一段主旋律部8小節 A B の2楽句の提示楽節と、続く C の前置楽詞と D 楽句 E 後置楽詞は、応答楽節8小節です。
なんと A 楽句の冒頭から、「音取」の最後の減五度下降跳躍が出て来ました。従って「音取」終止に続くブリッジは、旋律の予動提示だったわけです。そしてその部分は G・TP�の第一下和音と、D・TP�の第一下三和音との多調性だった、と見ること が出来ます。
そこで A 楽句1Bの類推曲調は、G・TP�となっていますが、本質的には括弧 内のD・TP�の方が正解で、そのまま2Bまで曲調を持続した方が、曲調としては安 定感があります。しかし中世の楽人たちには、TP�と言う今日的曲調感覚のあろう筈 はなく、旋律的頭音本位の合竹で、Ci s と言う16分音符は、旋律的派生音で、合竹の対象となっていなかったわけで、旋律音 g" に対応した合竹十のなかに変格として、統合されていたものと思われます。
ところで冒頭の合竹十の音組織に、ご注意下さい。そこには本来の最低音の Fi s が欠けています。この Fi s は旋律音のg" に最も近い短二度の Fi s で、流石に気になったのでしょう、これは体験的感性の正解と言えます。しかもこの Fi s を除いたことにより、合竹の分析構造が一変し、譜例(154)の(イ)D・TP�と、(ハ)の D・TP�との集合体と言う多声音となっています。もしここに本来の十の音組織であっ たなら、なんとしてもその違和感は隠しきれません、せいぜい評価は適応程度のところ で、楽曲の始まりから響態としての説得力が、弱いものとなってしまいます。Fi s を除いた合竹十は、まさに整合として楽曲の始まりらしい対応となっています。
続く A 楽句の2Bから、 D 楽句の1Bまで総ての合竹の最高音は、Fi s"' が通奏されています。これは旋律音より大分離れての高音密集ですので、遠隔多調とみれ ば許されますし、また余り障りとはなりません。但し B 楽句2Bの合竹下だけは、Fi s の複合音程の重複でもあり、これだけは只ひとつの不適合で、その他の合竹は適 合か適応と評価することが出来るでしょう。
そして D 楽句4Bから、 E 楽詞の2小節間に持続される合竹十には、再び Fi s が除かれています。このことからも冒頭の十は、決して偶然の所為ではなく、意図的所 産であったことを物語っています。この終楽段3小節の十 Fi s 欠けは、整合であることは間違いなく、始終を異端の創意で飾っています。
さらに本楽曲の双調は、呂旋法とされていますが、双調の g" から始まって、またその音で終わっているところからの、調号と思われますが、古代から旋律には呂旋法 はなく、その音列式上の律音階本位に、楽曲が構成されていることは、これまでの課題 曲ごとにご説明申し上げてきましたが、本楽曲もまた決して例外ではなかったことを、改 めて確認した次第です。そこで今後は一切、伝統的調号は楽理の対象とはしないとして も、略々間違いないと思います。それならば当楽段のように、類推する曲調が、G・T P�で始まって終わっていれば、これは主調性として見て良いかと言えば、そうでもあ りません。
双調の呂旋法(五音)は、譜例(154)の(ヘ)に示して有りますが、この音列上 の完全五度上の伝統的階音名徴(D)を主音として、その転回複合音程上に譜例(15 4)の(イ)D・TP�、その重属音列上にE・TP�Scale の成立が見られます。この(イ)の音階式上の二つの曲調のいずれかが、本楽曲双調呂の旋律的主調性と考えら れます。そうなると終止音のg" は、中間音では終止感は得られないところから、D・TP�の第2核音終止と見るべきです。
ところがこの第1や第2核音終止は、楽節的中間終止としての解決感しか得られませ ん。そこで E 楽詞の1BでD・TP�として、一応の終止を果たし、次の最終2Bで G・TP�に戻して、2BのD・TP�を属音調と見立てておいて。G・TP�とすれ ば主調感的終止感、換言すれば下属調終止という、仮装終止形とした次第です。またこ の終止形は、現代の邦楽や俗楽などの、常套的手法でもあります。
[譜例・158]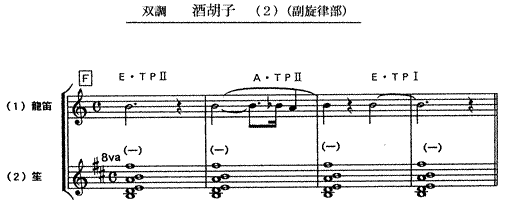
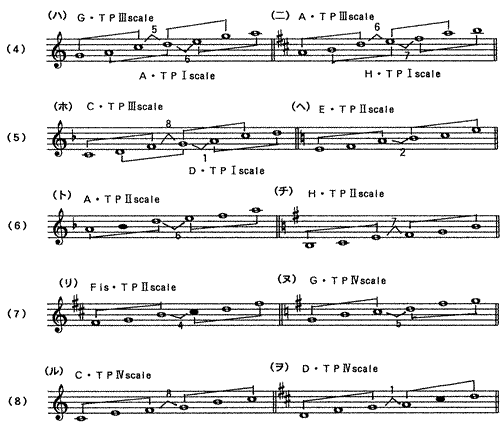
双調 酒胡子 (2)(副旋律部)
譜例(158)は第二大楽段のうち、副旋律部前楽節 F G の2楽句8小節、そして中間楽節 H 楽詞と I 大楽句の8小節です。
前の主旋律部との大きな違いは、陰音階で始まって終わっていることです。前楽節を 展開形とし中間楽節を類化展開形と、旋律的特質を名付けた意識の変化が、曲調の上に 截然と表現されています。陰音階という当時としては未知の曲調に、律に対する展開と いう形容名詞としたものとも、思われます。
合竹で特に気になるところは、 I 大楽句の2Bでしょう。これと同様の対応は前楽段の D 楽句の2Bでも見られます。当然この合竹は、旋律音のg" に対応されたものですが、その音は小節の最終の16分音符という、大変時価の短いものです。しかし その短いg" が fa(f" ) sol(g" ) la(a" )と言う、3音の旋律の中間解決形となっていて、短いながら旋律的核音であることは、間違い有りません。その解決音に対 応させた双調の十は、楽理的選択としては正解です。また最低音のFi s は、旋律が大きく揺れ動いておりますので、余り障りとはなりませんので、その評価としては辛うじ て適合、つまり適応より高いものとすることが出来ます。
その他の合竹については、当2楽節を通して最高音 Fi s は、陰音階が主流であるが故に、前楽段より一層障りとなって、残念ながら整合の評価は一つもありません。学 習者各自でよろしくご検討下さいますように、省略に代えてお願い申しあげます。
ともあれ雅楽管弦の中でも、最も古調を伝えると言われる『酒胡子』の解釈と検討を 終わって、有名無実の楽理時代の、体験美学的叡智と、感覚的不確実性を、現代的楽理識から確かめることが出来ました。