Ⅰ 平調宮(律)『越天楽』
現在雅楽管弦と言えば、先ず第一に誰でもが思い浮かべる旋律、それがこの楽曲『越 天楽』と言ってよいほど、一般的に膾炙されている楽曲です。
どちらかと言えば、この曲は唐曲のなかの小曲として分類されているようですが、そ の伝来については、確かな資料も口碑もありません。
近古代から中世の初め(1.012~1.106)にかけて、時恰も国風化時代、朗詠と前後し て今様と言う外来歌曲が、巷間に盛んに歌われていたと言う記録もあり、それらがやが て朗詠と共に雅楽に取り入れられ、朗詠の歌物と違って、今様は旋律だけが取り入れら れ、雅楽管弦の中に組み入れられた、と言う説もあります。
またこの楽曲は、平調の他に黄鍾調や盤渉調などもあって、いかに奏楽の機会が多かっ たかを物語っているようです。
各調別に、多少の味付けとしての曲趣の違いや、楽式的違いがあるとしても、旋律と して見れば大同小異です。なかでも、平調が原曲とも言われています。
それでは平調『越天楽』の旋律総音域譜表から、例によって検討してみましょう。
[譜例・138]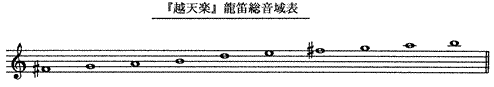
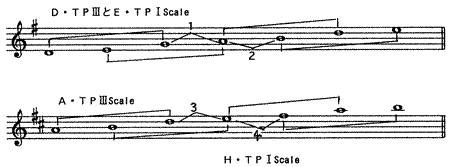
『越天楽』龍笛総音域表
前頁の譜例(138)は旋律楽部の龍笛の『越天楽』総音域譜表です。そして上記の 譜表は総音域譜表を整理して、使用音列式に改定したものです。さらにその鍵結びの長 2度間隔の部位で、DJが成立する可能性のあるところ、参考までに1番から4番まで、 その位置順を付けたものです。これを手掛かりとして、次の譜例(139)のような二 つの律音階と陽音階の成立を見ました。
[譜例・139]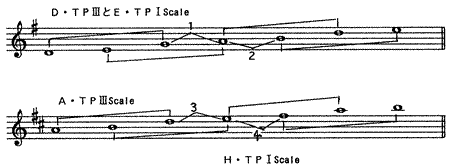
なんとこの音列式からは、この4種類の曲調しか解析できなかったのです。つまり副 標題ともなっている調号、平調宮の律音階〔譜例(132)の(ホ)を参照〕がありま せん。この音階機能としては重要な、第2中間音つまり導音の Cis が、旋律音の中には全く見あたりません。従って主調性はE・TP�ではないことは、確かと言って良い でしょう。この楽曲は、譜例(139)に記されたD・TP�、E・TP�、A・TP �、H・TP�のいずれかが主調性となるとの、予測を立てて間違いないようです。
それでは続いて、『越天楽』の楽曲そのものの、曲調を類推する前に、奏楽的資料の記 譜法について、ご了解を得ておかなければならないことがあります。対象となるべきも のが管弦楽の楽器様式には、楽部別の併行和声と言う曲趣が全くありません。ユニゾン かヘテロホニーと言う、つかず離れずの併行進行が、常套的手法とされています。従っ て旋律音(ここでは龍笛譜)と多声楽部の代表として笙の合竹譜だけを検索すれば、そ の殆どを知見する事が可能です。そこで旋律部の曲調の類推と、合竹の多声併行との相 関関係を、今後の管弦楽曲の解明の対象にすることにしました。そしてこの二つの楽曲 2部譜の、記譜様式としては、その実際の奏楽響態を記譜すると、次の譜例(140)の ような奏楽譜表となってしまいます。
[譜例・140]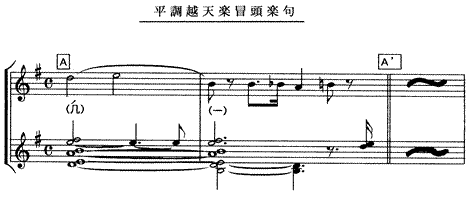
平 調 越 天 楽 冒 頭 楽 句
上段が龍笛(管楽部)、下段が笙の合竹と単管複管の、多声進行状況です。例えば上段 の2Bの2拍目の、付点の裏のb' の16分音符はmi からre に下降する中間の、半音下行に近い曖昧な経過音です。こうした音律的揺動は、雅楽や邦楽等によくある、独 特な曲趣で”塩梅”と呼ばれる、奏楽技法の一種です。つまり旋律進行上の、支配的曲 調とは余り関係ない、ユリとかスリとかいった感覚の派生的無律音で、音階組織として はその前後の音に吸収されて、考えられているものです。曲趣であって曲調としては、極 めて希薄なものです。
また下段の合竹譜の1Bの、3拍4拍の表まで架かる la の、強調性持続音や、2Bの4拍の表まで続く、mi とsol の2声のその裏の高音部16分のsol とlaの先行音などが、奏者の恣意に任せた強調音です。旋律の音に対応する合竹の多声組織と、大筋に 於いて響態そのものを把握しておきさえすれば、これらは瑣末的な問題です。
こうした側面的技法や構造を整理して、曲調的理解のより鮮明さを指向し、今後の管 弦課題曲は、次頁の譜例(141)のような記譜様式に、改定させていただきましたの で、何卒ご了承下さい。
[譜例・141]
平 調 越 天 楽 (1)
A 楽句の1Bの、sol からla の上行旋律はA・TP�のDJと見て、楽曲の始めに相応しい安定感を持たせました。そして続く2Bもmi - re - mi は、完全四度の下降跳躍を生かして、曲調をE・TP�に変えて、その第三核音解決を図りました。
続く A' 楽句の1BはA・TP�のDJとも見られますが、4拍目の下降の sol は、次の2Bで解決感を強調するための、導音経過音と見れば、核音より中間音の方が 経過音としての不安定性があり、より効果的です。そこでA・TP�の併行陽音階、H・ TP�にして次の2Bで、E・TP�とすれば完全なる解決を得られます。
これまでの2楽句4小節の旋律解析を通して、 A 楽句2小節の二つの2音旋律が、第 1動機でその第2動機が、 A' 2小節に渉る2音旋律の、上音解決と言うことになります。
そして B 楽句の1・2番括弧で囲んだ4小節が A 、A' で提示された第1第2動 機のバリエーション、展開楽節の部分と考えられます。ここの2Bでは、第1動機の2 Bで見られた跳躍下降旋律とは対照的に、緩やかな上行旋律と変えたもので、曲調も第 1動機2Bの、E・TP�の属調H・TP�と、併行基調D・TP� の二つで小節を2分しています。下降と上行、そして主調と関係近親調と、その変奏様式に顕著な対照性 を見せています。
また2Bの2拍目裏の8分音符の do は、3拍目以後の曲調D・TP�の先行音(sus)です。そしてこの2Bの3音旋律は、中間音解決形式です。
さらに『越天楽』前段の2楽節を通して、先ず各旋律の手法が、2音か3音のエンゲ メロディーで構成されて、進行していると言うことと、その解決が総て規則通りと言う ことです。エンゲメロディーの慣例律から、五音階音楽へと進化する音楽史的過程を、まさに浮き彫りにしているようです。
[譜例・142]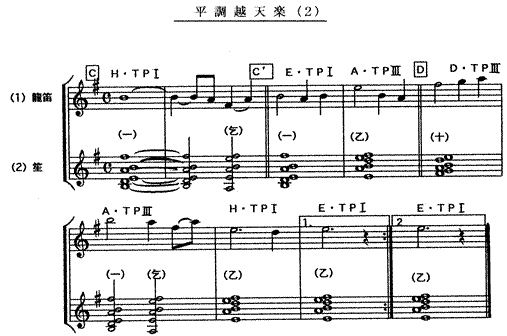
平 調 越 天 楽 (2)
『越天楽』の後段の解析に移る前に、もう一つ楽式論的四段形式について、説明を加え ておきたいと思います。
つまり前段の第1楽節 A A' の第1第2動機を、楽曲の起とすれば、第2楽節 B 以下4小節が承と言う展開形。そして後段の第3楽節 C C' は転と言う、強調的 新分野。そして続く第4楽節 D 以下4小節が結と言う、転によって印象的となった旋 律の収束。
それまでわが国の表現文化の主流となっていた、序破急と言う三段形式に、今様のよ うな歌詞の表現手法の、起承転結と言う四段形式が、雅楽管弦の器楽合奏作調の上に、投 影したものと思われます。
さて果たして第3楽節の C C' は、その転に当たる曲態をなしているかどうか、 まことに興味津々と言うところです。
まず後段 C 楽句1Bは、中間の mi の延長・持続で始まっています。2Bに移っても尚 mi は2拍の表まで継続され、その裏からre - si と完全4度下降し、再び短3度上行して一時的解決を果たしています。つまりこれは完全四度の3音旋律を2小 節で形成している、本楽曲で初めての曲態となっています。しかもまた、3音旋律は中 間音で解決するという、慣例律の法則まで墨守しています。
そして C' に移って2Bの la - mi ・re の五度下降は la ・sol ,・ mi ・ re の経過的下降旋律の sol の省略形です。従ってここでは解決していません。辛うじてそ の4拍目を第1核音として、楽節の終わりらしい安定感を、瞬時とはいえ持たせたわけ です。楽節の終わりに主調ではない下属調となったのも、本楽曲では初めてのことです。 まさに転の曲態です。曲想的新分野の提示を見事に果たしていると言ってよいでしょう。
愈々最終楽節の D 楽句の結に移ります。第3楽節の終わりから急激に、六度跳躍し てからの上行旋律は、2Bの始めの高音の mi に達し、mi ・ re ・si の3音旋律は中