(八) 雅 楽 管 弦
本講座基本編の最後に、本慣の中国大陸に無くて、朝鮮半島とわが国のみに進化発展 した純粋な器楽合奏、雅楽管弦の曲調を究明することにします。
中国の六律
六呂の12種類の曲調が、わが国に伝わってから、一世紀の時を経て六調子に統一さ れ、今日に伝える、いわゆる雅楽の六調子は、雅楽管弦の曲調において、最もその主流 をなしていると言って良いでしょう。
従って当項の各曲調別の楽曲を解析することによって、調号的動機と楽曲そのものの 曲調的実態も、改めて究覈し尽くしたと言って、決して過言ではありません。
前項の歌曲物の場合は、声曲中心の解析に終始しましたが、器楽合奏という響態の推 移を、その本歌とする曲趣から思量して、旋律器楽部と併行和音としての笙の合竹との 相関関係を、無視することはできません。
そこで今一度改めて、前記第六項の《日本雅楽の曲調》の第3章の一読を敢えて慫慂 する次第です。少し逆行のようでも、かえって理解を早め、将来のために資するものが あると思います。
さて対象とする課題曲には、それぞれの調号を代表するものとして、まず平調(律)か ら『越天楽』、壱越調(呂)から『武徳楽』、太食調(呂)から『長慶子』、さらに双調(呂) から『酒胡子』、黄鍾(黄鐘)調(律)から『拾翠楽』、水調(呂)から『鳥急』、そして 盤渉調(律)から『青海波』を選びました。
またここで改めて説明するまでもなく、上記伝統的各調号は、糸楽部の調弦用とした もので、笛楽部の旋律との関係性は、旋法的主音として対応を、考えられるとしても、支 配的曲調とは全く関係ないと見るべきでありましょう。
特に笙の合竹に於いては、壱越調の呂旋法を基調として、漢の十二律顕出順の音列式 の、複合音程の上に構成された11種類の多声音と単音管鳴により、旋律音に対応した、 各調共通の多声音が中心となっている、ということです。これがまた体験的成り行きと して、無意図的多調性を生んでいるわけでしたが、わが国の雅楽管弦の場合は、果たし てどうか、これから再確認することになります。
その前に先ず、雅楽の伝承者達の間で、今日まで笙楽者たちの虎の巻とされてきた、合 竹の活用表を検討してみましょう。[次頁(譜例・136)参照]
[譜例・136]
音階名の下の升目の中に記された、小文字の実音名は、参考までに筆者が推判し記入 したものです。それでもまだ笙管の配列順と奏者の手順に従った図式としても、一般には煩瑣の極み限りなし、と言ったところなので、改めて筆者が、上記活用表を解読し整 理して、各調の基本的五音七声音列式の各音に、対応させた譜表としたものが、次の頁 の譜例(137)です。
[譜例・137]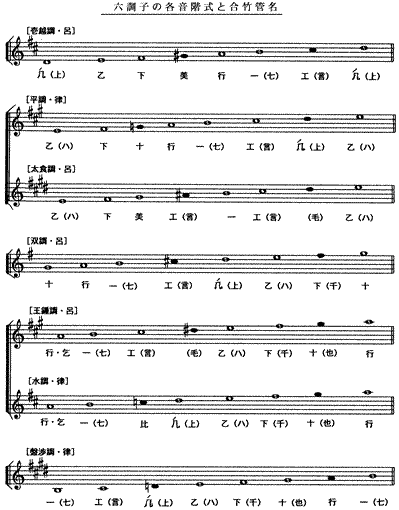
六 調 子 の 各 音 階 式 と 合 竹 管 名
こうなると各音階の単音と、合竹の対応関係が一目瞭然となったわけですが、実際に 楽曲を検討してゆくと、この通りではない部分も多く、古代の調号と楽曲そのものの調 性の齟齬は、そしてその要因は、当雅楽管弦の各調を検索するうちに、確かなものとなっ てくるものと思います。
要するに合竹は、その調号の如何に関わらず、その旋律音のひとつ一つに対応されてい る、という点に注意していただきたいのです。従って各調ごとに共通の合竹が存在する ことも、当然の結果であるとも言えるわけです。
なお譜例(137)の括弧内の管名は、高音域の甲音にのみ、単音で併奏される管名 です。つまり笙の楽部の奏楽は、合竹という手法上の多声音と、単独の管音とで構成さ れているものです。