俋丏楴塺擇挷
丂媨撪挕妝晹偵尰嵼傑偱揱偊傜傟偰偄傞壧嬋偺嵟屻偵丄強堗楴塺偺俀挷巕丄暯挷媨偲斦 徛挷偺幚懺傪夝愅偟丄夒妝壧嬋晹栧偺堦墳偺夝柧傪廔傢傝偨偄偲巚偄傑偡丅
丂楴塺偲尵偆惡嬋暥壔偼丄拞崙偺撿憊乮1.127乣1.279乯偐傜尦戙乮1.271乣1.367乯丄偦 偟偰柧乮1.368乯偺懢慶偺崰偲側偭偰丄桗乆偦偺嬋懺傪姰惉偝偣丄悽乆戙乆偺庲惗摍傪拞 怱偵惙傫偵墘彞偝傟偨晽挭偱丄偙傟偑暯埨挬偺拞婜崰杮朚偵揱傢傝丄摉帪偺岞嫧婱懓傗 柉娫偺庲惗丒暥壔恖偨偪偺娫偵丄惙傫偵壧傢傟偨傕偺偱偡丅
丂拞崙偺屆揟揑帊暥偺拞偐傜丄偦偺梫嬪傪嬦塺偡傞偲尵偆條幃偱偁傞偲偙傠偐傜丄偦偺 寍懺偼懡暘偵暥寍揑偱丄嬋庯偲偟偰偼壧梬偲尵偆傛傝壧塺偲偄偆傋偒傕偺偱偡丅傑偨偦 偺楌巎揑堄媊傪巚偊偽丄崱擔偺堦斒揑帊嬦傗楴塺偺憤徧偲偟偰偺嬦塺摍偺丄暎尮偲偟偰 婎杮揑堿壒奒偺嬋挷偺丄掕拝偲妋棫傪壥偨偟偨丄尨惡嬋偲尒橍偡偙偲偑偱偒傑偡丅
丂偦偟偰戝曄嫽枴傪妎偊傞偙偲偵丄摉帪偼偦偺墘彞偡傞嬋懺偼摨偠偱傕丄塺偢傞壧帉偺 僕儍儞儖偵傛偭偰徧暿偟偰偄偨偙偲偱偁傝傑偡丅帉揑戣嵽偲偟偰娍帊傪嬦偢傞応崌偵尷 傝丄楴塺偲柤晅偗丄榓壧摍傪嬦偢傞応崌偵偼彞壧偲屇傫偱丄滲慠偲墘彞摦婡偺堘偄傪椶 暿偟偰偄偨丄偲尵傢傟偰偄傑偡丅
丂偝傜偵偦偺嬋挷揑悇堏傗嬋懺傕丄偄偯傟傕堦掕偟偨傕偺偱偼側偔丄墘彞幰偨偪偺壒棩 揑慺梴偲丄暥寍揑嫵梴側偳偺廗崌偵廬偭偰丄嬌傔偰帺桼偵丄偟偐傕帊暥傗壧偺帩偮塁媟 傗撪梕偵懳墳偟偨丄帺慠側嬋庯傪埲偰懜偟偲偟偰偄偨傛偆偱丄懡暘偵屆戙偐傜嵼栰偵揱 鎢偝傟偰偄偨丄姷椺棩揑壧塺姶惈偑戝偒偔摥偄偰偄偨傛偆偱偡丅偦偺嬋挷偙偦堘偭偨偲 偟偰傕丄寍懺偲偟偰偼屆戙僊儕僔儍偺壒愡庡媊偲傑偙偲偵椶帡偟偰偄偨傕偺偲丄峫偊傜 傟傑偡丅
丂偦偺潑庹婜偵偟偰婛偵俋侽庱偺嬋悢偵払偟丄偦偺屻嵜攏妝傗柉娫揱彸偺崱條偲摨條偵丄 尮壠丄摗壠偺俀棳偵傛傝娗彾偝傟偨傕偺偲側傝丄憃曽偱嫞偭偰嬋悢傪慟憹偟偰丄尮壠偱 侾侽侽梋嬋丄摗壠偱偼俀侽侽庱傪悢偊傞偵帄偭偨偲尵傢傟偰偄傑偡丅
丂嬤屆戙偐傜拞悽偵偐偗偰丄偁傜備傞堦斒揑昞尰暥壔偐傜夒妝傑偱偺晽挭偱偁偭偨丄崙 晽壔偺塭嬁傪庴偗丄強堗乽晬暔乿偲尵傢傟偨娗尫偺彆憈偑壛傢傝丄獾丒鈾丒馊饷丒棿揓偺曇惉偵傛傞敽憈偺宍懺偲側偭偰丄杮娧偺拞崙偱偼巚偄傕傛傜側偄丄壺楉側傞娗尫壧嬋 偺嬁懺偵傑偱恑壔偟偰偟傑偭偨偺偱偡丅
丂偙偆偟偨廗崌偵傛傞宱堒偺拞偵丄師戞偵婍妝揑壒棩悇堏偺漼旾傪偆偗偰丄嬋懺傗嬋挷 傕夵掕偑孞傝曉偝傟丄撈摿側嬋庯偵掕拝偟偨傕偺丄偦傟偑強堗惡嬋偺夒妝壔偺孹岦惈偱 偡丅
丂傑偨堦曽偱偼丄岞嫧婱懓偨偪偺幮岎揑墐惾壧塺偲偟偰傕丄寚偐偡偙偲偺弌棃側偄廗懎 寍懺偱傕偁偭偨傛偆偱丄偦傟偑夒妝娗尫婍妝偺堦斒壔偺抂弿偲側偭偰丄傢偑崙偺幮夛堦 斒偵傢偨傞丄弶傔偰偺壠掚壒妝帪戙傪寎偊傞偙偲偵側偭偨偺偱偡丅帪妴傕揱彸幰偺擟偵 偁偭偨摗尨攷夒偺妝棟偺晛媦妶摦偵偼丄偦偺栶妱傪壥偨偡妴岲偺懚嵼偩偭偨偲尵偊傑偟傚 偆丅
丂偟偐傕摉帪偼丄奜棃偺抦尒偵傛傞妝棟偑拞怱偱丄嬋挷揑堄幆偲偟偰偼楥棩偺俀椶偵尷 傜傟丄堿慁丄梲慁偲偄偆嬋挷偑懚嵼偟偨偲偼尵偄側偑傜丄慜幰偺偄偢傟偐偺挷崋偺拞偵 娷傔傜傟偰偄偨傛偆偱丄廬偭偰婍妝墘憈忋偺挷崋偼丄扅偦偺庡壒偺傒傪帵偟偨傕偺偲尒 傞傋偒偱偡丅嬤悽偺帪戙偵姰惉偝傟偨嶰枴慄壒妝偺庡挷偑堿壒奒偱偁傝側偑傜丄堿慁丄梲 慁偺徧暿偺傕偲偵丄偦偺婡擻惈偺堘偄偑妋棫偝傟偨偺偼丄柧帯埲屻梞妝偑桝擖偝傟偰偐 傜丄偦偺挿抁挷偺塭嬁傪庴偗偰偐傜偺偙偲偩偭偨丅偲尵偆楌巎揑幚忬偐傜傕暘偐傞傛偆 偵丄柤徧偑晅偄偰偐傜偺懚嵼偱偼側偔丄妝棟偺応崌偼尦乆懚嵼偡傞婡擻偵懳偡傞丄嵎堎 偵梌偊傜傟偨柤徧偲尵偭偰傛偄傕偺偱偡丅廬偭偰乽堿慁偼棩慁偐傜恑壔偟偨乿偲尵偆傛 偆側愢偼乽巼怓偼愒惵偺偳偪傜偐偑慜偵偁偭偨乿偲抐掕偡傞傕偺偵摍偟偄傛偆側栤戣傪 巆偟傑偡丅
丂偝偰尰嵼傑偱丄惓幃偲偟偰揱偊傜傟偰偄傞楴塺偺侾侽悢嬋偼丄柧帯偺巒傔乮1.858 乯崰丄埢彫楬桳椙乮1.906 杤乯偐傜丄摉帪媨撪挕偵彽惪偝傟偨丄奺抧偺妝恖偨偪偵揱偊傜傟 偨傕偺偱偡丅
丂偦偺俀庬偺嬋挷傪戙昞偟偰丄暯挷媨偐傜亀壝扖亁乮廽乯偲斦徛媨偐傜偼亀懽嶳亁乮嶳悈乯 偺俀嬋傪壽戣嬋偲偟偰傒傑偟偨丅
嘥丂暯挷媨亀壝扖亁乮廽乯
丂昞戣偺亀壝扖亁偲偼丄屆戙拞崙偺姱恖偨偪偺嵟忋媺偺廽媀帊暥偐傜丄惏傟傗偐側忣姶 傪塺傫偩晹暘偺梫嬪偱偡丅
俈尵愡偵傛傞忋壓偺俀嬪偐傜峔惉偝傟偰偄傑偡乮壓婰帊暥嶲徠乯
壝扖乮廽乯 幱橆
壝扖椷寧焎柍嬌 漭嵨愮廐妝枹墰
丂偦傟偱偼愭偢丄楴塺暯挷媨偺憤崌惡堟昞偐傜椺偵傛偭偰専摙偡傞偙偲偵偟傑偡丅
乵晥椺丒侾俀俇乶
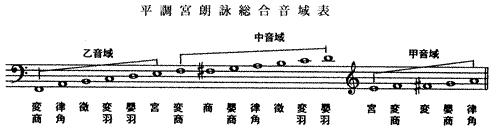
暯 挷 媨 楴 塺 憤 崌 壒 堟 昞
丂慜弎偺捠傝暯挷媨偲偼丄憈妝忋俤偺壒棩傪庡壒乮媨乯偲偡傞偩偗偱丄嬋挷揑愝掕偱偼 偁傝傑偣傫丅忋抜偺幚壒惡堟昞傪惍棟偟偰丄崅壒晥昞忋偵堏偟偰壒楍幃偲偟偨傕偺偑壓 抜偱偡丅
丂偦偟偰偙偺壒楍幃偐傜夝愅偟丄惉棫壜擻側壒奒傪椶悇偟偨丄師偺晥椺乮侾俀俈乯偵偼 乮僀乯偐傜乮僿乯傑偱偺丄崌寁侾侽庬椶偺壒奒偱偡丅
乵晥椺丒侾俀俈乶
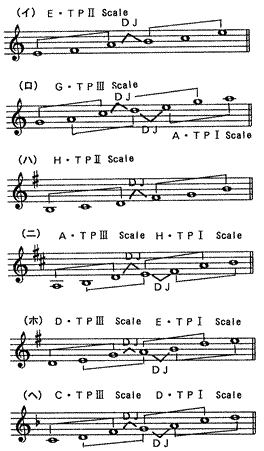
埲忋惉棫偟偨奺壒奒偺拞偱俤乮暯挷乯傪庡壒偲偡傞傕偺偼丄乮僀乯偺俤丒俿俹�偑扅堦偮 偱偁傞偲偙傠偐傜丄偙偺嬋挷偑庡挷惈偲偄偆偙偲偼棯乆娫堘偄側偄偲巚傢傟傑偡丅偦偟 偰楴塺偲偄偆惡嬋偦偺傕偺偺丄暥壔巎揑娐嫬幮夛傪峫椂偵擖傟偰丄妝婍憈妝傪拞怱偲偡 傞棩壒奒傛傝傕丄偦偺暪峴挷揑梲壒奒偺曽偑丄姷椺棩揑栰庯偵晉傒帺慠側嬋挷偺傛偆偵 巚傢傟傑偡偺偱丄壽戣嬋偺嬋挷夝愅偵嵺偟偰偼丄偦偺揰廩暘側攝椂偑昁梫偱偟傚偆丅
傑偨摿偵亀壝扖亁偼丄楴塺偺戙昞揑妝幃傪帩偭偰偄傞偲傕尵傢傟偰偄傑偡丅偮傑傝墘彞 偺婡夛傕懡偔丄帊暥偺奿挷偲廽嵳惈偐傜丄掕拝傪壥偨偟偨傕偺偲巚傢傟傑偡丅
乵晥椺丒侾俀俉乶
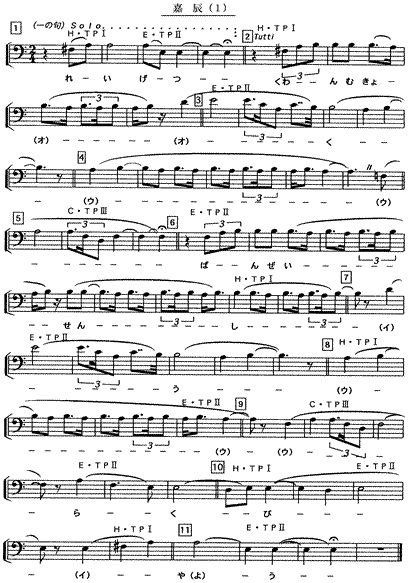
壝丂扖乮侾乯
丂
丂偙偺妝幃偼丄乽堦偺嬪乿乽擇偺嬪乿乽嶰偺嬪乿偺嶰晹宍幃偱偡丅奺抜偑偦傟偧傟姰慡廔巭 偟偰偄傞偲偙傠偐傜丄妝愡揑傛傝傕妝復揑嬋庯偲側偭偰偄傑偡丅廬偭偰杮島偱偼丄奺抜 偵懳偟丄撈棫偟偨妝復偲尒橍偡偙偲偵偟傑偟偨丅
丂偦偟偰帊偺慡暥傪姰彞偡傞偺偼丄乽擇偺嬪乿偩偗偱丄乽堦偺嬪乿偼忋偺嬪俈尵偺俁
尵栚偺乽椷寧乿偐傜乽嶰偺嬪乿偼忋偺嬪偺俈尵偺俆尵栚偺乽焎柍嬌乿偐傜庡彞幰偺僜儘 偱摫擖偟丄惸彞偵堏峴偡傞條幃偲側偭偰偍傝丄奺嬪憡屳偵戝摨彫堎偺嬋挷悇堏偱孞傝曉 偝傟傞偲尵偆斀暍宍幃偱偡丅
丂偙傟偼尰戙偺堦斒偵揱彸偝傟偰偄傞丄帊嬦傗楴塺摍偺壓偺嬪偺斀暍宍幃偺尨宍偲峫偊 傜傟丄梫嬪偺帩偮帊揑忣庯傪彯傔傞丄拞悽揑抦宐傪丄嫮偔姶偠偝偣傞嬋懺偱偁傞偲丄尵 偆偙偲偑弌棃傞偱偟傚偆丅
丂梊憐偳偆傝庡挷惈偼丄俤丒俿俹�偺堿壒奒偱偁傞偙偲偼丄媈偄偺梋抧偑偁傝傑偣傫丅偦 偟偰俫丒俿俹�偺梲壒奒偑懏壒嬋挷偲偟偰丄廔巭宍傪峔惉偟偰偍傝丄偟偐傕偙偺俫丒俿 俹�偺婎挷揑暪峴壒奒偑丄俙丒俿俹�偲尵偆乲晥椺乮侾俀俈乯偺乮僯乯傪嶲徠乴棩壒奒 偑丄壓懏壒庡壒偵摉偨傞偲偙傠偐傜丄忋壓偵傢偨傞懏壒婡擻偺暋崌挷偩偭偨偙偲偼丄堄 奜側敪尒偲偟偰崱屻偵丄怴偨側壽戣傪巆偡偙偲偵側傝傑偟偨丅
丂傑偨尰戙朚妝偺嶰枴慄壒妝偱傕丄偦偺杦偳偺嬋挷偑堿壒奒偲偦偺庡壒偲屲搙娭學偺梲 壒奒偑庡棳偲側偭偰偄傑偡丅偙傟偼擔杮恖偺楌巎揑嬋挷姶妎偲傕巚傢傟丄偦偺尮棳偺堦 偮偑拞悽偺楴塺偲尒偰丄娫堘偄側偄傛偆偱偡丅
丂偲傕偁傟丂侾丂妝嬪偺庡彞偺僜儘偵傛傞摫擖晹係彫愡偼丄傂偲愭偢 俫丒俿俹�偲俤丒俿俹�偱丄姰慡廔巭宍偱揨傔丄懕偔丂俀丂妝嬪偺愭傔偺 tutti 偐傜惸彞偺惡嬋偐傜夵傔偰丄摨嬋挷偺宱夁傪丂俁丂妝嬪慡懱偵傑偱奼戝偟偰偄傑偡丅偙偺巒傔偺俁妝嬪偵懳偟 偰丄妋偐側嬋挷偑採帵偝傟偰偄傞偙偲偼丄斲掕弌棃側偄傕偺偲側偭偰偄傑偡丅
丂偙偆備偆嬋懺傕傑偨丄朚妝偺壧偺弌抂偺忢搮揑條幃旤偺堦庬偲側偭偰偄傞傕偺偱偡丅
偙偺戞侾妝復乮堦偺嬪乯慡懱傪捠偟偰丄摿偵拲堄偟側偗傟偽側傜側偄偲偙傠偼丄 俆 妝嬪偺俁彫愡偱偟傚偆丅偙偙偱偼妝嬪偺巒傔偺侾彫愡栚偐傜丄俢丒俿俹�偲尵偆乲晥椺乮侾 俀俈乯偺乮僿乯傪嶲徠乴梲壒奒偱傕丄廩暘偵懳墳偱偒傞偲偙傠偱偡偑丄丄偲側傞偲俀彫愡 俀攺栚偐傜俁彫愡傑偱帩懕偝傟傞倖偺晹暘偱丄偦偺壒偑戞侾拞娫壒偲側偭偰丄晄埨掕姶 偼斲傔傑偣傫丅偟偐傕僼僃儖儅乕僞傑偱晅偄偰丄偦偺惡棩偑嫮挷偝傟偰偄傑偡丅偦偙偱傗傗埨掕搙偺偁傞拞娫夝寛傪巚峫偟偰丄俢丒俿俹�偺婎挷揑暪峴挷偺俠丒俿俹�偲尵偆 棩壒奒偵丄姼偊偰慖傫偩師戞偱偡丅
丂偮傑傝僼僃儖儅乕僞傑偱晅偄偰帩懕墑挿偝傟偨廳梫側壒棩偼丄偨偲偊拞娫廔巭偲偟偰 傕丄戞俀偐戞俁偺妀壒偱偁傞偙偲偑丄慁棩揑帺慠側埨掕姶偑摼傜傟傞偲尵偆傢偗偱偡丅偙 偆偟偨堿壒奒傪庡挷惈偲偡傞慁棩偺側偐偱丄 mi 偐傜 fa 傑偨偼 fa 傑偨偼 la 偐傜 fa 偲側偭偨帩懕壒偼丄堿壒奒撈摿偺拞娫夝寛偲偟偰峫偊傜傟傑偡偑丄丂俆丂妝嬪俀 彫愡侾攺偺棤偺 re 偐傜 la 偵忋峴偟偨帩懕壒偵偼丄懡彮晄帺慠側傕偺偑偁傝傑偡偑丄 嫲傜偔敽憈妝婍偑壛傢偭偰偄傞偐傜丄偦偺憈妝揑漼旾偺拞偱丄懱尡揑偵曄壔偟偨傕偺偐丄 杮娧偺抧拞崙偐傜偺嬋挷偺柤巆傝偲傕丄峫偊傜傟側偄偙偲傕偁傝傑偣傫丅
丂偄偢傟偵偣傛乽堦偺嬪乿慡懱傪捠偠偰姶偠傜傟傞偙偲偼丄梋傝偵傕嬋挷揑廂澥惈偑丄媡 偵慁棩揑偵偼扨挷偲側傝偼偟側偄偐丄偲尵偆栤戣揰傕側偒偵偟傕偁傜偢偱偡偑丄偦偺斀 柺丄墘彞幰偺堄幆偵傛偭偰丄帊暥偵懳偡傞嫽庯傪彯傔傞岠壥偲側偭偰偄傞偲丄尒傞傋偒 傕偺偱偟傚偆丅
乵晥椺丒侾俀俋乶
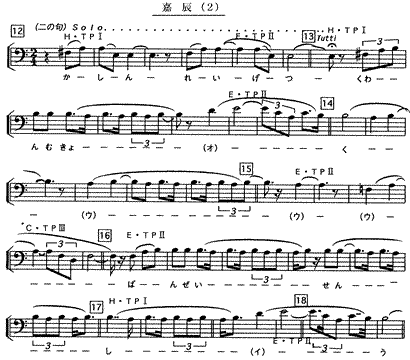
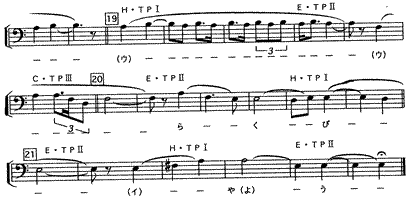
丂壝丂扖 乮俀乯
丂乽擇偺嬪乿偼慡偔乽堦偺嬪乿偺孞傝曉偟偵嬤偄傕偺偱丄嬋挷揑偵偼戝摨彫堎偱偡丅偟偐 偟帊暥傪姰彞偡傞妝復偼丄偙偺乽擇偺嬪乿偩偗偱偡偺偱丄嬋懺偲偟偰偼揱棃摉帪偺尨宍 偵丄嵟傕嬤偄傕偺偲巚傢傟傑偡丅
乵晥椺丒侾俁侽乶
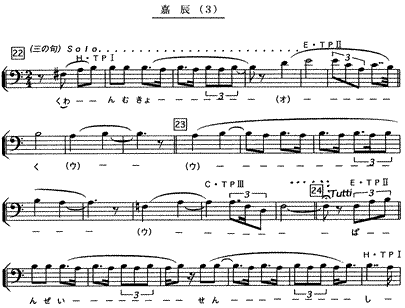
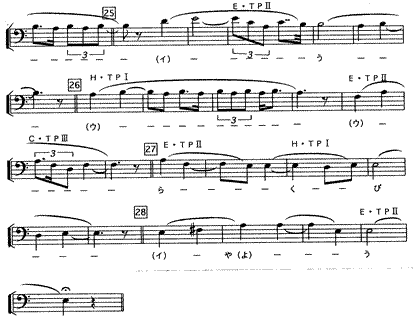
丂丂壝丂扖 乮俁乯
丂乽嶰偺嬪乿偱偼丄側傫偲尵偭偰傕庡彞幰偺僜儘偺妝愡偑丄奼戝偝傟偰偄傞偙偲偱偟傚偆丅 偮傑傝墑挿偝傟偨僜儘偺晹暘偼乽擇偺嬪乿偺梋忣傪挿偔帩懕偟偨偲偄偆偙偲偱偟傚偆丅
丂廬偭偰偙偺妝復偱偼丄 24 妝嬪俀攺栚偐傜惸彞偝傟傞丄壓偺嬪俈尵偑杮壧偱丄偦偙傪嫮挷偟傛偆偲偟偨慜敿偺丄挿偄摫擖晹偲尒傜傟傞傢偗偱偡丅
丂尮壠摗壠偺俀棳偵揱彸偲嫵庼偑埾偹傜傟偨偲偙傠偐傜丄擇幰嫞墳偺偆偪偵寍摴巚憐偑 熂梴偝傟弌偟偨丄摉帪偺幮夛揑攚宨偑丄傑偝偵晜偒挙傝偵偝傟偨傛偆側俁抜宍幃偺嬋懺 偲丄嬋挷偲傕尵偭偰傛偄傛偆側丄偗偭偟偰応摉偨傝揑側嬋庯偱偼側偄傕偺偱偡丅偳偆傗 傜惡嬋揑旤堄幆偺夎惗偊偺帪戙偱傕偁偭偨傢偗偱偡丅
丂偙偆偟偰帊暥傪壧塺偡傞偲尵偆昞尰暥壔揑峴堊偼丄暓嫵偺宱暥傪壧塺偡傞峴堊偲傕丄嫟 捠惈偑尒偄偩偣傑偡丅偙偺偙偲偼楴塺偺揱敠宱楬偵増偭偰丄挬慛敿搰偱傕杮娧偺抧拞崙 戝棨偱傕椺奜偱偼側偐偭偨傢偗偱偡丅
丂強堗瀽塖偲偐惡柧偲偐傛偽傟偨丄暓嫵偺媀楃壧塺偼丄傢偑崙偵暓嫵揱棃偺摉弶偐傜丄奺 帥堾偱惙傫偵峴傢傟偰偄偨偺偱丄偦偺壒棩姶偼丄挿偄悽戙傪宱傞偆偪偵壗帪偟偐崙柉揑 姷椺棩偺堦晹偲偟偰丄掕拝偟偰偄偨偲峫偊傜傟傑偡丅廬偭偰楴塺偺崙晽壔揑晽挭偺婎憌 偵偼丄偦偺壒楍幃偺堘偄傪椶暿偟偰崱擔峫偊傜傟偰偄傞丄棩丒梲丒堿偺屲壒奒偺暋崌挷 偑丄媀幃壧塺慁朄偺姷椺棩偲偟偰丄恑壔傪悑偘偰偄偨帪戙偩偭偨偲丄悇嶡偱偒偨師戞偱 偡丅
丂
丂