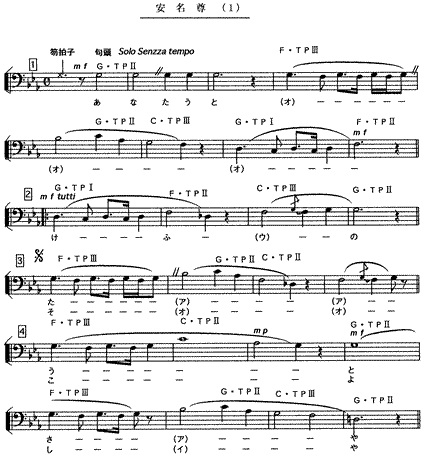8.催馬楽
中古代の後半、雅楽の各楽種が外来楽として我が朝に伝わった。第一国際音楽時代は 近古代後半にして本格的第二次国際音楽時代を迎えました。国風化という風潮に乗って、 古くからの固有声曲と外来器楽との習合による、雅楽歌曲の数々が、まさにそれである わけです。そしてその代表的な曲態曲趣が、催馬楽と総称される曲種と言ってよいでしょ う。
この催馬楽の各曲は、朝廷に貢献する織物や、魚貝類の乾物や穀物、そして貴重な生 活物資等を馬の背に乗せて都入りした、馬曳き人足たちが、郷土の歌霊を唱詠品柄しな がら御所の倉入りをしていたと言われています。
やがてこうした土俗的歌謡が貴族階層を中心に流行し、笏拍子・和琴・箏・琵琶・龍 笛・笙・篳篥などの雅楽管弦が、体験的に習合されて、次第に曲調や曲趣を整え、朝廷 内の管弦歌物の催しには、欠くことの出来ない縁起ものとして、代表される曲種にまで 進化したものです。
往事の文献に記された歌数の多さから、いかに当時の流行ぶりが盛んであったかを物語っています。
宇多天皇(1.272~’86)第八王子.一品式部卿敦実親王を流祖とする源家。従三位皇 太后権太夫博雅朝臣を流祖とする藤家の二流によって、平調宮(律)28曲・双調宮(呂) 37曲の多数が伝えられていましたが、その後足利時代に一時中絶され、今日伝えられ ている曲種は、寛永三年(1.626)に再現されたものと言われています。
本講の課題曲としては、平調宮(律)の中から『伊勢の海』。双調宮(呂)の中から『安 名尊』の二曲を二つの曲調の代表として選んでみました。その他の両曲調の曲種は、こ の二曲に大同小異で、曲調、曲趣の本質的解析はこれに尽きると言ってよいでしょう。
Ⅰ.平調宮『伊勢の海』
まず催馬楽平調宮(律)の総合声域表から、検討を加えて、その潜在的曲調を類推し てみることにします。
[譜例・115] 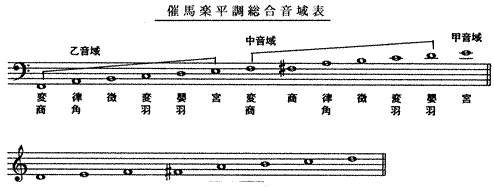
催 馬 楽 平 調 総 合 音 域 表
譜例(115)の上段は、実音に基づいた総合声域表ですが、下段は曲調解析用に、複 合音程を省略整理し、音列式として高音部譜表に転回したものです。
下段の単純化した使用音列式から、成立可能な五音階を類推すれば、次の譜例(11 6)の(ロ)の陰音階(E・TP�scale )と(ハ)の律(A・TP�scale ) と陽音階(H・TP�scale ) の三種の曲調が考えられるわけです。
[譜例・116]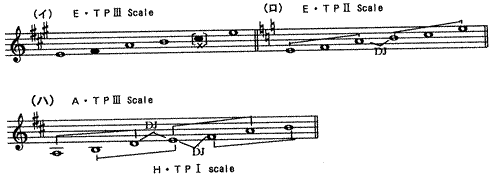
ところが器楽部の演奏者たちに指定されている曲調は、平調宮の律音階〔譜例(11 6)の(イ)参照〕です。歌唱楽部の旋律に使用されている声音のなかからは、この曲 調の第二中間音の C' i s が存在していないので、平調宮の(律)音階の支配力は、極 めて薄いと想定してよいでしょう。
従ってこれまで解析してきた、雅楽部の古代歌謡の各曲同様に、平調宮(律)であるE・TP�scale を基調とする、和琴の残留音(最終音)の響きから、歌唱楽部の頭 音の音取りとして、奏楽に移った、その曲調は主たる3核音を共通する、(ロ)のE・T P�か(ハ)の2種の律か陽(A・TP�&H・TP�)だったと推判する事が出来ま す。
こうした調号的齟齬は、中世の初めの調性感の不確実性を物語っていると、断定する ことは、現代的調性感の自己投入として、大変迷惑なことかも知れません。
東アジアの伝統音楽の器楽合奏様式の特徴でもある、ヘテロホニーと言う旋律と伴奏 楽の即興的ズレ、つまり付かず離れず(不即不離)と言った、縦(音程的)横(律動的) の揺れが、重要な曲趣の深さであり、情感的余残の味合いとする、広域的価値観の立場 からすれば、二つ以上の核音を共有する関係調による、無意図的多調性であると与えて 見るべきものでしょう。
しかし曲調的に同調した、縦の音階支配を意識した現代音楽が余りにも一般化した今 日、このままで従来の価値観を主張し、将来にわたってこれを墨守しきれるものではな いことも確かでしょう。調性感の展開する音楽を知ってしまった、聴いてしまった現代 の人々、そして未来の人々の普遍的価値観たり得ないわけです。
ともあれ、もう一つの音楽としての東アジアの音楽を、現代の価値観の中に展開する 方途については、この先少しづつ試みることにして、続いて愈々本題の『伊勢の海』の 解析に移ることにします。
[譜例・117]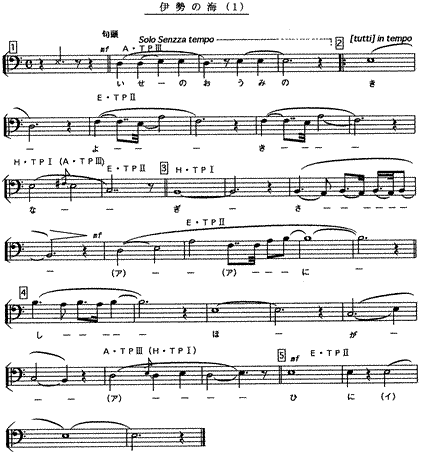
伊 勢 の 海 (1)
催馬楽平調律『伊勢の海』は、先ず和琴による音取りのあと笏拍子の空拍子が鳴って
1 楽句の2小節目から、音頭(主唱者)のソロによる句頭が始まり、2 楽句の t u t t i で全員斉唱の歌詠に移ります。
譜表上部に記されたTP記号は、筆者の類推した曲調の加筆です。
さて 1 楽句2小節目から始まる旋律はdとeの2音で構成されたエンゲメロ ディーで、法則通りに上高で解決しています。当然ここはA・TP�のDJ部〔譜例(1 16)の(ハ)の上、参照〕と考えるべきでしょう。そして 2 楽句の3・4小節のf・e・a・fの3音旋律の中音解決は、E・TP�〔譜例(116)の(ロ)参照〕 の第1中間音です。
こうした fa とか si のような中間音解決は、陰音階の特徴でもあり、無意識なが ら主調的安定感を最終音とするべき調性感が色濃く感じられます。
続いて7小節目のcの持続の3拍目に fis の装飾打音があり、当然これはA・TP�の
第2中間音と見るべきですが、次の8小節でE・TP�の第2中間音の経過的解決のあ と、 3 3楽句のはじめから、H・TP�の第1核音が初めて現れますので、その予 音(サステンス効果)として、敢えて7小節目はH・TP�の曲調を借用した次第です。 この借用調の意義は、次の 3 楽句前半のH・TP�と後半のE・TP�への推移で、 もっとも自然な拡大型として、大きな効果を見ることが出来ます。
そして 4 楽句の1小節から6小節までは、前楽句のE・TP�の曲調を持続して、 続く7・8小節は、H・TP�でも効果がありますが、第1楽節の終局部に近いので、句 頭の部分の曲調を再現しておいて、最後の 5 楽句全小節を、E・TP�で中間終止 的解決を図ってみました。
これはつまり典型的な仮装終止と言えるもので、今日の邦楽の常套となっている終止 形の原型が、はやくも雅楽歌曲のなかに現然として存在していたわけです。
またこのような歌曲の終止形が定型のように出現してくると、もはやこれは定則性と 見做して、よいように思われます。そして雅楽歌曲の旋律の曲調の共通性として、核音 を共有する3種の曲調が、基本的調性感となっていると言ってよいでしょう。当章の課 題である催馬楽平調宮の歌曲には、これまでの類推から、基本的3種の曲調に敢えて機 能性を見出して換言すれば、E・TP�を主調として、その完全5度上の第3核音から 成立する5音階が、上属音的調性であり、完全4度上の第2核音から成立5音階が、下 属音的調性だと見ることもできます。即ち上属音的調性とは、H・TP�であり、下属 音的調性はA・TP�の 五音支配の機能であると、見て取れるわけです。
[譜例・118]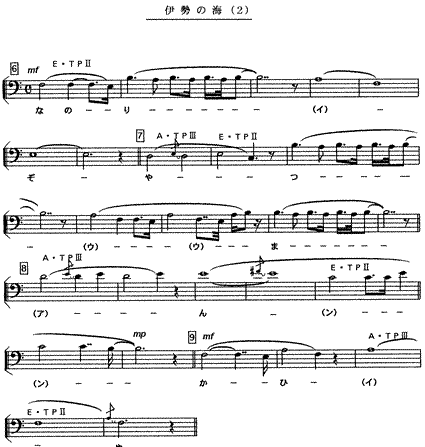
伊 勢 の 海 (2)
『伊勢の海』の第2楽節の 6 7 8 9 の全楽句を通して、E・TP�の主調としての安定感は、確実なものと感じられます。そしてA・TP�の調性との対 応を繰り返しながら、旋律的には高音域構成が主題となっているところから、感性的に は明確なる聞かせどころ、明らかにサビを意識した楽節と見てよいでしょう。
[譜例・119]
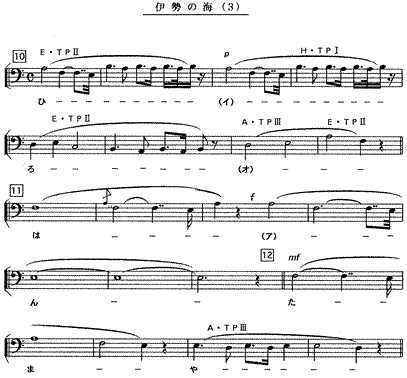
伊 勢 の 海 (3)
この第3楽節に移って、途中 H・TP�のの曲調を配しながら、次第に旋律は下降方向に移行し、最低音域に達しています。これは前楽節の高音域旋律に対する、変化形と してとして対照的意識が動機だったことを物語っています。。
10 楽句7小節が、その対照的旋律であり、曲調としても4小節目のH・TP�が、A・ TP�に対照されたものと言えます。
そして 11 楽句の5・6・7小節から 12 楽句の3小節目までは、前楽節からの 上行下降の変化型旋律の、激動感を柔らげるための余情的静動を意識した、平行的エン ゲメロディーと見られます。
さらに 12 楽句の4・5小節のA・TP�の曲調は、次なる第4楽節[譜例(120)] 初頭の2小節の関係曲調に移行するための、経過楽句的中間終止形としての、機能性を 強く感じさせます。
[譜例・120]
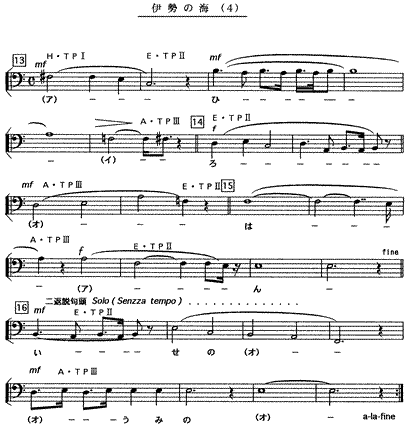
伊 勢 の 海 (4)
さて 13 楽句の始めに、問題の声域表の黒符頭( fis) が、正式に現れてきました。当然この音は核音でなければ、旋律的説得力が薄められます。
従ってH・TP�の第3核音と見た次第です。そして6小節目の3拍裏の fis の短二度上行は、次の第 14 楽句1小節目の d,e へと、連続して考えA・TP�としたわけです。
続く 14 15 楽句はE・TP�とA・TP�2種の曲調を繰り返し、仮装終止 の安定性を強調する結果を生んでいます。
歌曲の1回目は引き続き、次の 16 楽句に進み、レピートしてからの2回目は、
15 楽句で完了です。つまりこの 16 楽句は、楽式としては換頭と呼ばれている、句 頭部3小節に戻った際の、変奏的拡大楽句の様式の部分に当たります。当然ここは曲趣 の蘇生感を昂めるために、音頭のソロで演唱されるわけです。
Ⅱ・双調宮『安名尊』
所謂催馬楽の律呂と言われている、2種の調号のうち、双調宮『安名尊』は、呂旋法 (音階ではない)と伝えられています。 時として呂旋法の代表的な曲調のように俎上 に
乗せられてきた曲趣でもあるところから、敢えて本講の呂旋法の課題として選んだ次第 です。
呂旋法(5音七声)の音階としての支配的機能の曖昧さは、前にも第四項の第2章で も説明しましたが、その音列式の複合的延長音列上に、第3核音、つまり完全五度上に 成立した、所謂徴の律音階、そのTP式のDJ部分が下方に転回されたものと、解析結 果として確認できたことを、改めて思い起こしていただきたいと思います。
果たしてその律音階が、催馬楽双調宮(呂)の総合声域表の中から、成立させ得るか どうか、検討を加えてみることにしましょう。
[譜例・121]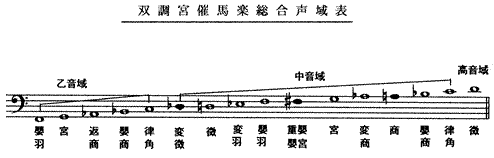
双 調 宮 催 馬 楽 総 合 声 域 表
はじめの低音部記号の音列表が、現在の雅楽部に伝えられている全声域表です。二段 目の音列式は筆者が内在曲調を解析する便宜として、上下に複合された音を省略し、音 列式として整理し、高音部譜表上に転回させたものです。そして三段目の最後の譜表は、 参考までに副題双調宮の呂の五音七声を、音列式として示したもので、その符頭上部に 記されたバツ印は、2番目の声律式に全く存在しない音です。
たとえばこの音列式から完全五度上の、徴の律音階を成立させようとしても
のような図式となり、TP構造の中でも第1中間音(E)と、第3核音(A)が無い ところから、徴の律音階であるD・TP� scale は、全く成立し得ないことが明らかです。従ってその並行音列式の呂旋法も、また存在できないことも推測できます。副題 の調号として伝承されてきた双調宮の呂は、この総合声域表からは考えられない調号だっ たと、言ってよいでしょう。つまり器楽伴奏上の手法の都合から、名付けられたと見る ことも出来ます。
今日の調性概念とは、全く別の概念からの動機で伝えられてきた曲調の呂は、有名無 実と確認することが出来たわけです。それでは実楽としての、声曲の曲調実態はどうか、 先ず2番目の整理された音列式から解析類推を進めてみましょう。
次の譜例(122)の(イ)から(ホ)までの各段に示された、各音階の成立が可能 であることが、予め考えられます。
[譜例・122]
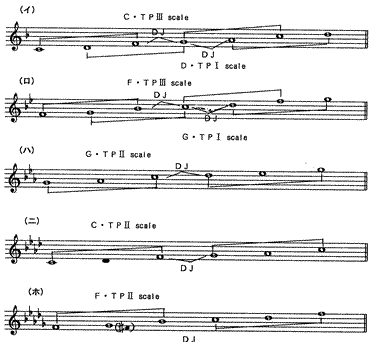
(イ)の段の律音階(C・TP�)と、その併行調の陽音階(D・TP�)。(ロ)の段 では律音階(F・TP�)とその併行調の陽音階(G・TP�).そして(ハ)(ニ)(ホ) 格段の陰音階(G・TP�-C・TP�-F・TP�)、合計7種類の曲調までに、展開 することが出来る多調音列式です。
そして総合声域表の黒符頭音は、前にも説明したように経過音的付加音とされている ところから、黒符のない(ロ)と(ハ)の段の3種の曲調が、基調的支配音階だという ことは、想像に難くありません。双調宮とは、(ロ)の陽音階とも、(ハ)の陰音階とも 見ることができ、古代の我が朝の雅楽寮の文献には、未だ陽旋陰旋と言った曲調的分類 意識が現れていないところから、呂とは陰陽の複合調に与えられた、過渡期的曲調だっ たのかも知れません。
いづれにしても、総合声域表上の音列からは、(ハ)のG・TP�scale が最も確率性が高い曲調と、予測することが出来たと見て、略々間違いないでしょう。
[譜例・123]