5.東 遊 歌
東遊の歌とは、上古代わが国の都から東方に当たる地方の、風俗、土俗的舞踊が服属 儀礼の芸能として朝廷に入り、その後雅楽寮の管掌のもとに伝承され、一時期平安朝の 国風化の影響を受けて、雅楽の管弦が加わって一変し、その後長らく跡絶えていたもの が、文化年間に復活され今日に至っています。
従ってその芸態としては、総て古代のままとは言えないまでも、往古の実態を想像す るための資料としては、役立つものであることは間違いないようです。
歌と和琴の演唱部は、中世より京都の多氏、笛・篳篥及び舞は南部の上・辻・芝・奥・ 東・窪・久保氏などの、左右の近衛府に属した楽人達が、累代相伝して来たものが、現 在の宮内庁楽部によって収斂されたものを、本講の課題としました。
奏楽の次第は、『一の歌』『二の歌』『駿河歌』『求子歌』『片おろし』などで、舞は4人 乃至6人の円舞で、前段に駿河舞、後段が求子舞を舞い、これを総称して諸方舞、そし て後段の求子舞だけの場合を片舞と呼ぶことになっています。
前段の『駿河歌』までの各曲調や曲趣は、『神楽歌』と大同小異の、所謂『琴歌』風で すが、特に『求子歌』に、総合的曲趣の特徴が顕著なところから、この曲を解析してみ ることにしました。
なをこの『求子歌』は、古くから加茂神社や石清水・春日などの近畿地方の各社に奉 納された際、和歌を奉納するための儀典の曲種とされていたことからも、その特異性が 考えられるわけです。
また万葉集の巻第16の、和琴の弾奏によって、河村王が歌ったと言う記述もあり、古 代社会の普遍的曲態でもあったと、見て取れるわけです。
それでは先ず、本題に入る前に、『東遊歌』の全声域表から、検討を加えてみることに します。
[譜例・98]
譜例(98)は『東遊歌』に使用された全音域表です。上段音列の下に示された盤渉 (H)を宮とした漢式階音名は、そのまま調性の主音として見做せば、次の譜例(99) の(ハ)段に解析された、H・TP� scale (盤渉調陰音階)を主体とした音列の複合表と考えられます。
[譜例・99] 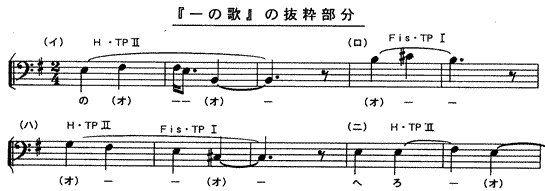
そしてこの表の中の黒符頭(経過音)の Cis(商) は、D(重属音)関係にある(イ)段か(ロ)段の、E・TP � scale (平調律音階)かFi s ・TP�scale (下無調陽音階)の第2中間音か、第3核音に該当するものの現われと見てよいでしょう。
いづれにしても、本課題の『求子歌』にはこのCi s が 出て来ませんので、その前に、この音の使われる序曲『一の歌』の一部を抜粋して、一応の確認をしておくことに します。
[譜例・100]
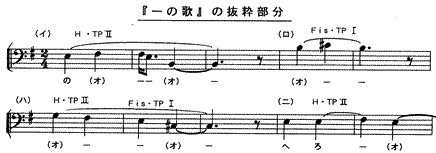
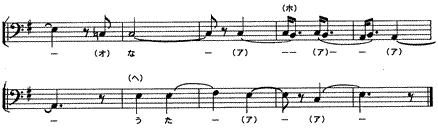
譜例(100)の(イ)楽句3小節は、『一の歌』の途中で、中音域のeから fis に上行し、再びeを経てhまでの完全四度下降跳躍しています。この一時解決部分は、譜 例(99)の(イ)の第3核音か、又は(ロ)の第2核かのどちらにも見て取ることが 出来るわけですが、続く次なる(ロ)楽句1小節の2拍目に、初めてCi s が出て来て当然この楽句は、前述のE・TP� scale (イ)か、Fis ・TP�(ロ)のいづれかですので、従って(イ)楽句3小節は、譜例(99)のなかで残る調性でもある、(ハ) 段に解析されたH・TP� scale (盤渉調陰音階)の第1核音解決形と見たほうが、曲調としては最も自然な移行が得られるでしょう。
そして(ロ)楽句に潜在する曲調は保留して、次の(ハ)楽句3小節に目を移してみ ましょう。
ここでは明らかに、下降音列式の様相でCi s で中間解決をしています。その1小節目のgからfi s の短二度下降は、譜例(99)の(ハ)H・TP� scale の第2中間音から、第3核音への移行以外は考えられません。そして続く2小節目の、eか ci s に短三度下降しての中間音解決は、経過音Fi s を軸として、Fi s ・TP�scale に転調されたことを物語っています。これは共通する核音の機能が、第3核 音から第1核音に移行したことによる移調法で、陰陽の音階構造の接合転調と言うわけ です。
続く(ニ)楽句の終結音のcは、H・TP� scale の第1中間で、(ニ)楽句5小節から(ホ)楽句の1小節まで、H・TP� scale で通して、その2小節目でAの解決は、E・TP� scale の第2核音と見るべきでしょう。従って(ホ)楽句の2小節 目から、続く(ヘ)楽句の2小節目まで、E・TP � scale を持続し、その3・4小節のe・c・eの 下降上行は、H・TP� scale と言う主調性に戻って、完全なる偽装解決と言って良いとおもわれます。それでは譜例(98)の声域表の中の、黒符 頭のCi s についての調性的機能を一応は解析できたものとして、愈々本題に進むこ とにします。
[譜例・101]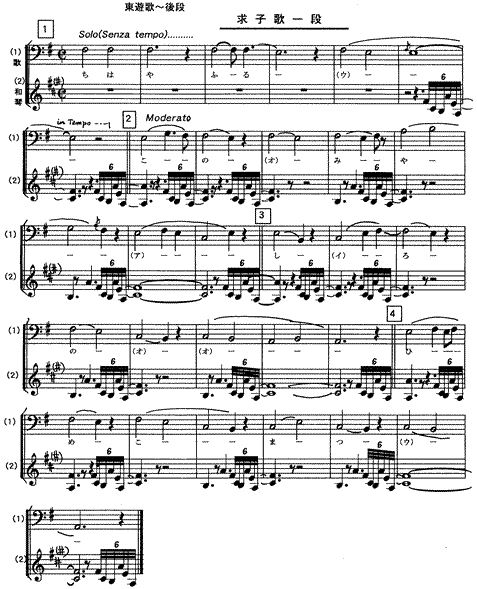
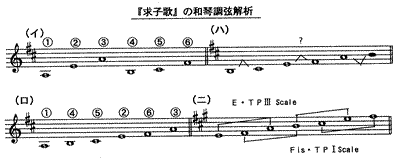
譜例(101)の『求子歌』は、二段楽部形式の琴歌となっています。まず下段の和 琴のアルペジオの掻き手の響態から、その調弦法を検討することにします。
譜表の(イ)は、1の弦から順に6の弦までの音律を、そのまま譜表としたものです。 そしてその下段の(ロ)は、音高順に整理してその音列から調性解析の手懸かりとした ものです。さらに(ハ)は(ロ)の音列からDJの可能性を持つ、長二度の音程連続の 部分を印したもので、中央の e' から f''is の長二度には、それに続く短二度も短三度、さらに長二度も存在しないので、DJ成立の可能性は先ず無いと見ることができま す。
従って h からcis 、その複合音列上の a' から h' の二カ所にDJの可能性があるものと類推できます。こうして解析できた音階が、譜表(ニ)の上下括弧で結ばれた、E・ TP� scale と Fis・TP� scale の二つの調弦であることが判明しました。
それでは前の譜例、『求子歌』一段に戻って、その冒頭の詞章「ちはやふる」の歌い出 しから考えてみましょう。
当然のことながらこの前に、序奏として和琴のの弾奏による歌出の手があり、残響保留音は、a とa’ の2音となっています。初めの音律は f' is ですが、残響のaよりアルペジオの最終音�Eの弦の fis から、音取りは可能です。
しかしこの歌唱声律の fis は、1 楽句の3小節も持続され、曲調としての核音的機能が濃厚です。従って和琴の持つ調性E・TP�から、重属音程上の陽音階、Fis ・TP�
scale が演唱意識のなかにあったと見てとるべきでしょう。そしてその4小節目のeか ら、E・TP� scale となるか、或いはこの4小節目の下降は、経過的音律と見て、 F is・TP�の陽音階を保持し、次の5小節からE・TP� の律音階とすれば、4小節の下降のときは、先行音であり2調の共通音サスペンスとなって、理想的荘重な効果 が得られるでしょう。
そして 2 楽句の1小節の2拍目の、gからfis の短二度下降には、明らかに陰音階の中間音から核音への移行が感じられます。従ってそのまま4小節間を、H・TP� scale の第二・第三核音による、DJ 構造の持続的延長であり、同時進行の和琴の響態との間に生ずる、調性の併行感が、東アジア独特の関係調の習合によって生ずる、多調 性音楽の実態であると、見て取ることが出来ます。
続く5小節のaからhの上行は、E・TP�の第2、第3核音、さらに6小節の g から f'is の下降部分がH・TP � 、その2拍目の装飾的スキップ小符のaは、前調性の第二核音残留的付加音と見れば、別に問題はありません。そしてこのH・TP�の曲 調は、楽句の終わりまでの3小節を持続されています。
それにしてもこの部分の、和琴の残留中低音の Cis は、旋律音のCと半音の抵触は、気にならないこともありませんが、和琴の断続性と、同時音の fis があるため、この上音の倍音として吸収されてしまい、伝統音楽として見れば許されることでしょう。
そして 3 楽句は、全く前楽句の曲調の繰り返しです。続く 4 楽句は、1小節から4小節目までが Fis・TP�、次の5小節目がE・TP�、そして続く6小節から終 わりまでが、H・TP� を保持して次の二段に進みます。
こうして『求子歌』一段の全体を通して、その歌出しの冒頭の、主唱者音頭の独唱に よる自由テムポの部分だけに、陽音階的曲調が存在し、その後は、律と陰音階だけの多 調性音楽として一貫されていました。このことは何を意味しているかと申しますと、古 代の野にあった頃の『求子歌』は、陽音階が主体ではなかったのかと、見ることも出来 るわけです。そうした在野の歌が朝廷に入って、和琴の持つ律音階的掣肘をうけて、そ の土俗性をしだいに失ってしまったように、思われてなりません。
『求子歌』〔次頁(譜例102・求子歌二段)参照〕二段楽節の 5 楽句の、はじめから3小節目まではE・TP�、続く4小節目から7小節目まではH・TP� 、そして次の8小節目で再びE・TP� に戻っています。そして 6 楽句は、1小節から6小節ま でがE・TP � 、次の7・8小節でH・TP� となり、最後の 7 楽句は1小節から4小節までが、H・TP� を持続し、5小節目だけがE・TP�、次の6小節でH・TP� に戻って、そのまま7・8小節と持続して終わっています。
[譜例・102]
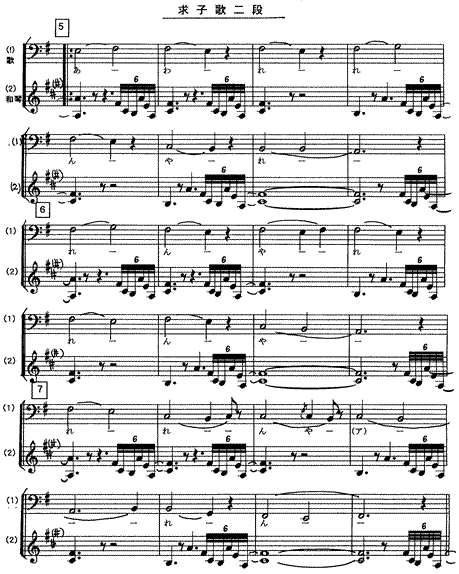
[譜例・103]
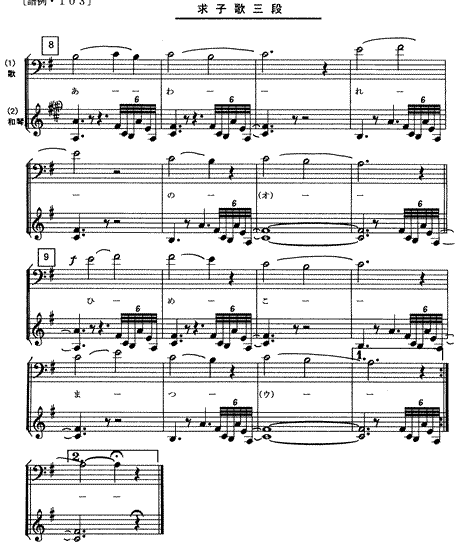
さて三段に移ってはじめの 8 楽句から、高音域声曲となっています。その1小節から3小節までは、H・TP� の陰音階で始まり、そのまま7小節目までは、同調を持続し、終わりの8小節目でE・TP�で解決。そして続く 9 楽句からの2小節目までH・TP� 、最終の1番・2番括弧でE・TP�に戻れば、所謂偽装終止形が成立し ます。
このように一段から三段までの、古代歌謡琴歌の実態は、和琴の持つ律音階をベース に通奏し、多調性と同時に併行する声音域の変化に、ある種の価値観を持たせながら、無 意識の中の普遍性でもある、陰音階への定着を模索していたかのようでもあります。