4.神楽歌『阿知女の作法』
神楽歌とは文字通り、かむくら(神の座)としてのわざおぎ、つまり神を招き入れる 上古代からの、伝統的儀式歌でもあります。宮廷内の祭祀楽としては、最も古く神聖な 固有音楽と言われています。
古来から夜を徹して、数多くの曲数があり、『音取』『寄合』『庭燎』『阿知女』『採物』 『榊』『韓神』『其駒』と進めて、終わることが吉例とされて来ました。
なかでも『庭火の歌』に継ぐ『阿知女の作法』は、重要な神態の作法と言われ、その 芸態としての特異な作法は、古代シャーマンのメカニズム、人格転換(トランス)憑霊 (ポゼッション)脱魂(エクスタシー)の三要素の、習合性を思わせるものがあります。
こうした神聖視された古代からの芸態には、創意工夫を最も嫌うと言う、歴史的習性 があり、そうした因襲と言ってよい程の保守性が僥倖となって、今日改めて楽理として の究明に際し、古代声曲の実態を模索するための、恰好の資料と申し上げて、けっして 過言ではないでしょう。
[譜例・96]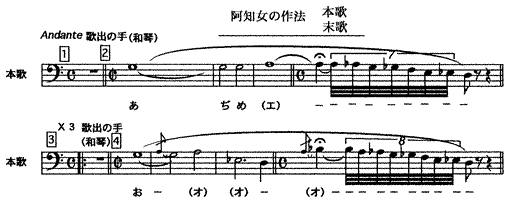
譜例(96)が、その『阿知女の作法』の前段の4楽句です。1 と 3 楽句は、『庭火の歌』同様調弦の、和琴による「歌出の手」です。歌唱楽段の本歌とは、主たる歌唱 者で独唱部、末歌とは、それに従う伴唱者のことで斉唱部のことです。この前段譜は、本 歌だけの楽句で記されています。
2 と 4 楽句の歌唱譜は、中音域のg(律角)から始まって、夫々の4小節目は クロマチックで下降して、低音域のd(宮)で終わっています。
この2拍目の As から Es、Aから Es までのクロマチックは、唱声の移行する通過状況を示したもので、極めてレガートに2音間グリスのような、歌唱法と言った方がよい ものです。従ってその過程符記音は、調性的には無関係と考えられるべきで、始音のa と終音のdとの下降完全五度に、留意すべきでしょう。
2 楽句の2小節から3小節にかかる、長二度の上行をDJ部分と見れば、この楽句 全体を譜例(87)の2段下部のD・TPI scale で、通奏することが出来ます。
そして和琴の歌出の手に続く 4 楽句は、D・TP�scale 始まって、3小節目に移って、第1・第2・第3核音の共通音を利用して、D・TP� scale に移れば幽玄な転調が得られます。
[譜例・97]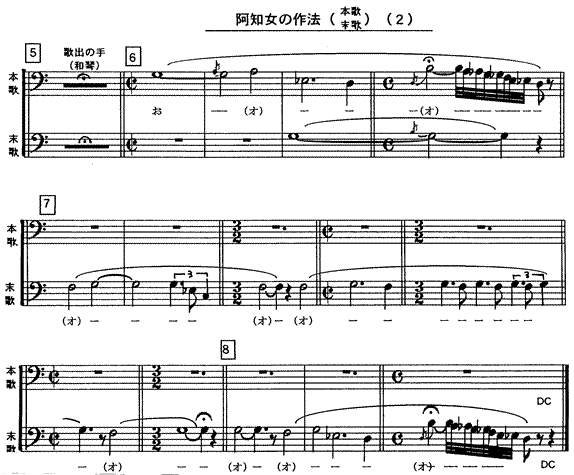
譜例(97)は『阿知女の作法』の後段です。 6 楽句は、前段の 4 楽句と全く同じ調性割で、3小節からの末歌の斉唱が加わります。
そして 7 楽句の末歌のfからg上行長二度が、新たな曲調のDJ部分と見れば、 そのまま 8 楽句の1小節の終わりまで、譜例(87)の4段目下部の、C・TP� scale
の陽音階の曲調が持続できます。続くその2小節目から、Gの核音移動と、EsとBを 共通中間音として、D・TP � scale の陰音階に戻って、所謂偽装終止形で解決していることが、感じられます。
さらにD.Cで 1 楽句に戻ってからの2回目は、本歌と末歌の歌唱楽部の受け持 ち楽部が入れ替わって、演唱される様式になっています。
勿論本曲は、陽旋とか陰旋とか言った、現代的調性感が、全く意識されなかった古代 のこと、器楽を伴った慣例律声曲と言った方が確かです。そうした往時の美意識を、遣 された実態を通して、たとえ慣例律と言えども、無意図的にせよ、曲調性と言う音階機 能に支配されていなければ、楽曲としては成立し得なかった。その確認のためにも、現 代のペンタトニック調性感に照合してみたわけです。
そしてこれまでの幾つかの曲例を通して、自然人類的声律感でもある慣例律声曲は、2 音構成から始まって、3音そして4音5音と次第に進化したと言われている。所謂エン ゲメロディー展開の法則性と言うその核単位は、長二度の2音構造によるDJ部分から始まった、と見て取ることが出来たわけです。そして長二度による3連続音は、TPの 第1中間音、第2核音と第3核音と、その支配的機能を構成していったということが出 来るわけです。そして曲調を支配する第1核音は、最終的に顕音され、安定感成立と同 時に、ペンタトニックの完成が感じられます。従って十二律成立後制定された呂の階音 名〔(譜例・89)の上段〕は、楽器としての音律名であって、つまり声曲と同音程関係 を表わす目的で、そこに示された宮は、TPscale と照合された第1核音と関係はなく、楽理としてはなんの意味を持たない、つまり宮を音律の基準とした音程関係の代名 詞程度と見ておくべきでしょう。