(G)一の合竹
この合竹もまた、壱越調呂の五音までの音組織から構成された、5音6声の拡大音域 型合竹です。この転回による音域拡大型は11種のなかでも、協和と調性の整った、最 も勝れた和音形態と言ってもよいものです。
[譜例・80]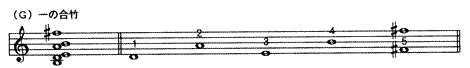
一の管の音律、盤渉( h ' )を、七の管の h '' と重複させたところが、譜例(77)の(イ)(ロ)の3種の曲調に対応し、その旋律音としての、盤渉( h ' )に最も適応しています。
(H)行の合竹
この合竹も、前条の一の合竹と全く同じ音組織から構成された、5音5声の密集型合 竹です。従って対応する曲調も前条の3種ですが、第2音の黄鐘( a' )が、旋律の中に現われたものに、適応するところが違ってきます。
[譜例・81] 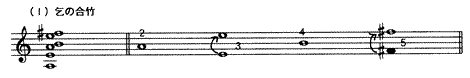
(I)乞の合竹
この合竹は、第2音の黄鐘( a ' )から第5音の下無までの、4音のみで構成された4音6声の拡大音域型合竹です。
なぜ母調の基音である壱越( d ' )を省略したのか、つまり乞の管の音律の、黄鐘(d ' )を強調し、黄鐘調の呂旋法を志向して、つまり水調の曲調を単一に意図し、そ の主音の黄鐘(a' )に適応させるものでしょう。
[譜例・82]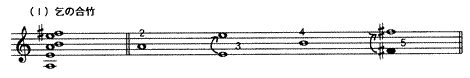
前条の行の合竹の拡大省略形です。また省略された壱越( d )が経過音的に響いたとしても、逆に補足による調和として、効果が上がることも考えられます。
(J)凡の合竹
この合竹もまた、壱越調呂の五音までの音組織から構成された、5音6声の拡大音域 型合竹です。
[譜例・83] 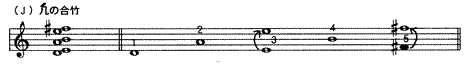
凡の管の音律は、壱越( d ' )であり、母調の主音でもあります。従って譜例(77)の乙の合竹と、全く同じ曲調に対応し、母調の楽曲の頭音と終止音の壱越に、最も 適応するものと言えます。
(K)比の合竹
さて最後の合竹の比は、美の合竹同様に、多調性不完全和音とも言えます。
[譜例・84] 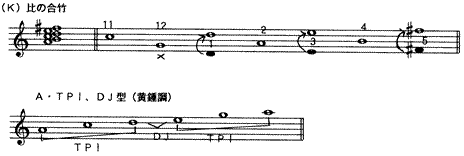
11番の神仙(c)を起音として、13番で1番に還元され第5まで7音律の中で、1 2番の双調( g ' )だけを省略した、6音6声の密集和音の合竹です。
名称動機となった比の管の音律は、神仙( c '' )です。我が国の奏楽規定の曲調とされる、4呂3律のなかにはこの音は、原則として出現しません。従って神仙の音律よ りも、適応させる旋律音は、壱越調呂の五音のなかにあるのではないか、と思われます。
ともあれこれで雅楽独有の響態を代表する音色の、笙の合竹11種の構成基準を概念 的にせよ、分析することが出来たわけです。これらが実際の奏楽の場にあって、実楽と してどのように対応しているかが、楽しみでもあり、最も楽理的要衝でもあるところで す。愈々東洋の生きている音楽の化石、雅楽実楽の解析に入ることにします。