(G)太食調の呂調弦
愈々六調子の例外の曲調として、太食調の呂調弦の実態を解析することになりました。
前条の説明通り、太食調とは呂旋法に与えられた、祖調としての敬称的代名詞でもあ り、大変豊かな曲調と言った意味まで含まれているようです。譜例(70)の楽筝の調弦譜表を見たところ、明らかにこれは平調の律調弦〔譜例(54)〕に類似し、同主音呂 旋法化した、バリエーションであることが判ります。
従ってその本質は、平調の律となんら変わるところがない、と言う見方が一般的です。 その説が果たして妥当かどうか、だとすれば敢えて例外として、太食調を設定する必要 はなかった筈です。
ともあれ、従来の通説や既成概念にとらわれることなく、本講の楽理尺度で解析する ことこそ肝要です。
[譜例・70]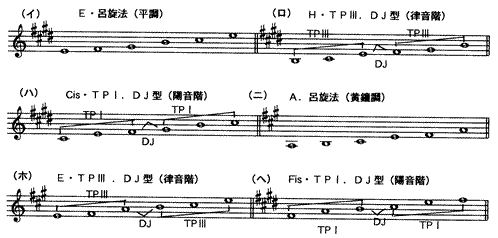
楽箏・太食調(呂調弦)
平調の律調弦〔譜例(54)〕と比較して、呂角(gi s )律角(a)の、押し手技法で発生した嬰律が、複合音程関係で2ケ所あることによって、その転調音域が、平調 の4種の曲調〔譜例(55)〕より、5種も増えて合計9種の曲調に達しています。〔譜 例(71)の(イ)から(リ)まで参照〕
[譜例・71]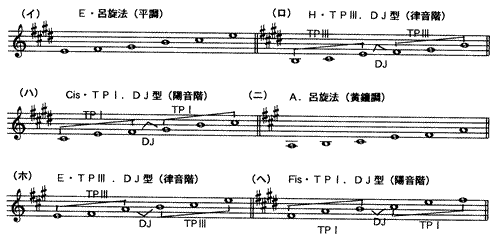
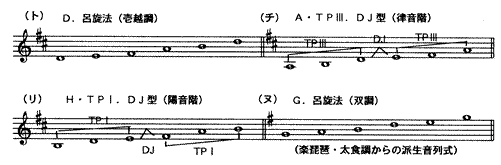
さて続いて同調に対応する、楽琵琶の調弦ですが、これは平調の律調弦をそのまま、呂 旋の曲調に転用したものです。
しかし各弦別の音列譜表では、全く同じ音律を利用して、奏者の音列意識の違いが、白 符頭の差異によって示されています。同主音の呂も律も、多調性という雅楽の響態の前 には、一体不二の相互関係の音列にあることを物語っているわけです。
[譜例・72]
楽琵琶・太食調(呂調弦)
この調弦の各弦別音律譜表からは、譜例(71)の9種のほかに、譜例(57)の8 種にさらに、譜例(71)の(ヌ)双調の呂旋法まで加わって、合計18種の曲調まで に、その転調音域を拡げられるわけです。
やはり太食調の呂は、平調律の進化された曲調として、六調子の例外と定めた所以も それに帰すべきものが、あったと見るべきでしょう。