(F)水調の呂調弦
古代わが朝で制定された、奏楽のための所謂雅楽の六調子とは、この水調までの6種 の曲調のことです。中国古代に定められた六呂六律に対応して、わが国では宴楽として の立場から、また器楽的掣肘もあって三呂三律と定め、これを六調子と総称して来たわ けです。このほかに例外として太食調があり、その本質的曲調は平調の律のバリエーショ ンと言われています。
ここで改めて、三呂三律の統合としての六調子の調子について、楽理的定義をしてお きたいと思います。先賢田辺尚雄氏の説によれば〈調子という用語には、古くから律と 調の二つの意味を持っている。〉と定義しています。本講の立場から、これを更に補足し てみれば、律とは十二律に制定された各音律のことです。この場合は律旋音階の律とは 全く関係ない、主音となる音律(実音)の規定と考えるべきでしょう。そして調(しら べ)とは、呂旋法とか律音階・陽音階さらに陰音階とかいった、旋律的曲調をさすこと になります。
たとえば壱越調の呂と言えば、その主音たる音律を壱越(d’)とする、呂旋法(do , re , mi , sol , la , do )の曲調と言う規定を意味します。またこの調性は、東アジ ア系奏楽の母調でもあります。そしてこの調号の同音列の延長線上にTPとDJの音階成立の尺度に適合する、律音階・陽音階の2種の曲調に展開することが出来ます。つま り壱越調の呂には3種の調(しらべ)が潜在していることを意味しているわけです。こ の3種の曲調の関係は、呂を母調とすれば、律音階は子調であり、陽音階は孫調に当た ることになり、中間の律音階(徴調)から見れば、陽音階は乞食調であり、それに相対 する呂旋法は太食調と言う、文芸的動機からの用語も発生して来ています。この乞食調 や太食調は、その曲調の発生経緯を叙情的共感性を転用した用語と、捕えることができ ます。
さて本題の水調とは、果たして何を規定したものか、当然十二律の中には水調という 律は存在しません。
三味線音曲の用語に、水調子と言う調弦法があります。一の糸の調律を実音Aにした ものが1本と名づけ、基本的音律は実音Hの3本で、これに従って記譜されることになっ ていますが、音律を次第に上げて8本(e)か10本(f i s )までが限度で、それ以上の調律にはオクターブ下(乙)の展開調弦で、水の11本(G)とか12本(Gi s )とか呼び、これを総括して水調子と表現されています。一口に浪曲の太棹の一の糸の、あ の揺れ動いた音色を水調子と形容するわけです。
即ち水調とは、水の音に似たゆるんだ音色、弦楽器特有の物理的現象の謂であり、そ うした現象を作るために一段と律を下げると言う、概念も併合されるわけです。
つまり物理的音色と低律概念と叙事的共通概念を通して、表現した用語でもあります。
[譜例・66]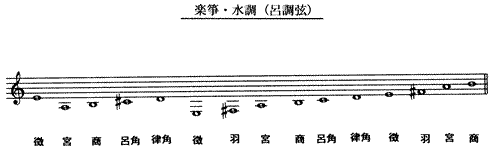
楽箏・水調(呂調弦)
前出の譜例(58)の律調弦と、譜例(66)を比較してみれば、一目瞭然呂角(C i s )と律角(d’)との違いだけで、あとは全く同音列構成であることが分かります。
勿論律音階に転調するためには、押しの手の技法で黒符頭の律角に発音させるだけで、 その転調音域が倍増される、譜例(67)のような結果となり、水調と規定した意義を、 色濃く感じられます。
[譜例・67]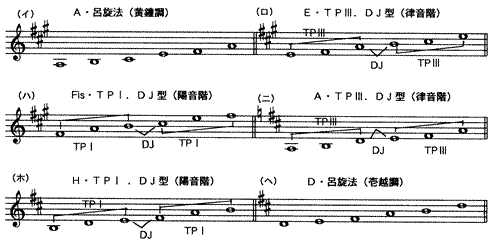
水調は黄鐘調に類似していると言われながらも、その1音の相違が、転調音域の側面 からみれば、遥かにそのふところの広さが判明したわけです。
[譜例・68]
楽琵琶・水調(呂調弦)
譜例(68)の各弦別音律譜表から、少数弦楽器特有の転回跳躍型旋律様式を考慮に いれて類推すれば、前の譜例(67)の6種の曲調のほかに、次の譜例(69)の21 種の曲調で、合計27種の曲調にまで、その転調音域を拡大することができます。
[譜例・69] 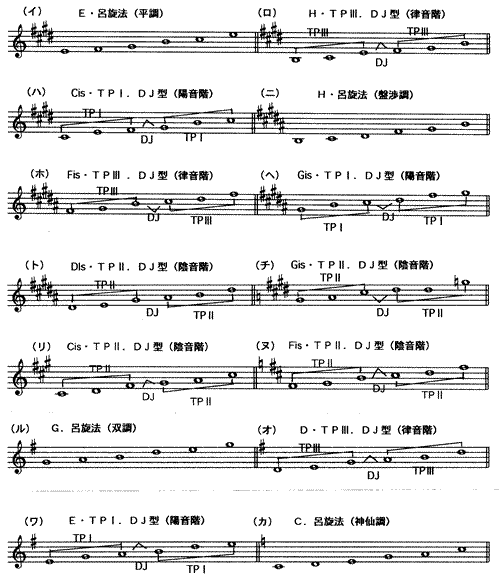
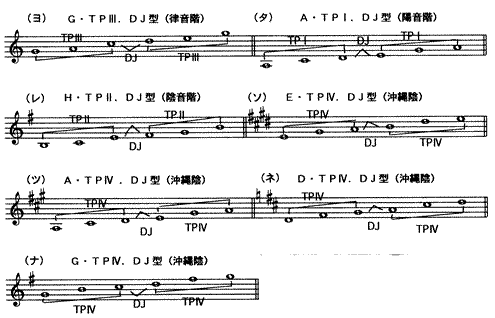
長二度とクロマチック音列を、その調弦音律の基調とする楽琵琶の構造的多様な対応 性に、改めて驚かざるを得ません。
楽琵琶から俗楽の琵琶楽、そして三味線音曲へと展開し、近世の代表する邦楽の発生 する要因は、雅楽の管弦奏楽のなかに息づいていたことが、愈々確かなものとなった、と 言ってよいでしょう。