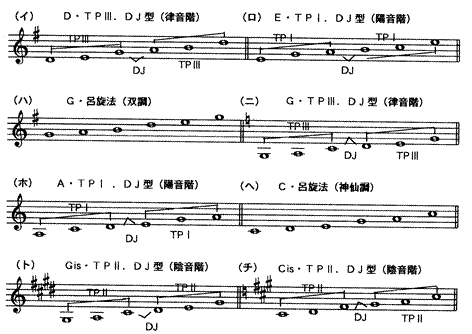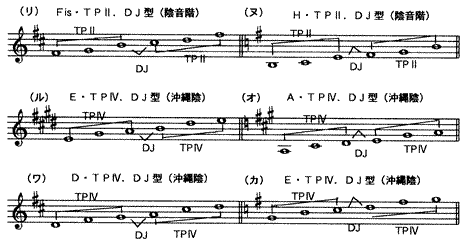(E)盤渉調の律調弦
盤渉調の律とは、Hを第1核音とする律旋音階のことです。〔(譜例(63)の(イ)参 照〕
譜例(62)の楽筝の調弦譜表は、盤渉調の律音階の調弦法です。
[譜例・62]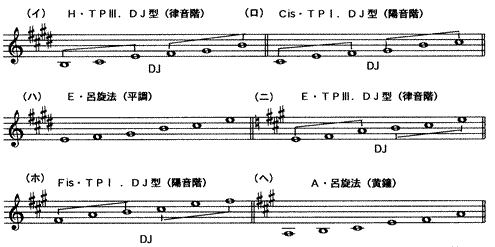
楽箏・盤渉調(律調弦)
この調律音列式の中から、譜例(63)の(イ)と、その重属音上の陽旋音階(ロ)を、 主調としての平行調が、推判されます。
そして黒符頭で示された嬰羽(A)が派生した場合には、その基礎調律音の羽(Gi s)は、同時的音列としては存在しないところから、譜例(63)の(ニ)と(ホ)の平行 調か、(ト)と(チ)の平行調のいずれかに転調されたものと、見るべきでしょう。
[譜例・63]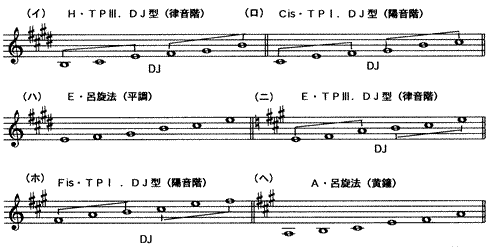
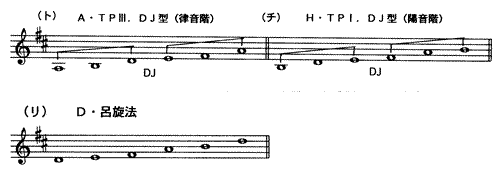
また当然ながら各調の共通音列式の延長上に、複合的基調として呂旋法、(ハ)(ヘ) (リ)の3種にまで展開することができます。
続いて同調に対応する、琵琶楽の調弦法が譜例の(64)です
[譜例・64] 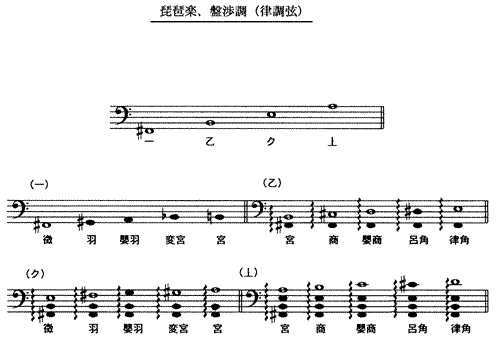
この各弦の音程関係が、総て完全四度から構成されていることは、4弦の撥弦楽器と しては、最も理想的な安定感と、多様的対応性が感じられるものです。一と乙とクまで の3弦は第3核音・第1核音・第2核音の関係にあり、上の弦の嬰羽(A)は、明確に 四度五度の自然的転調を示唆しています。
特にこの調弦の乙・ク・上の3弦は、三味線音曲の基本的調弦とされている、『三下が り』3本そのまゝの調弦関係となっています。
筆者は、我が国に三味線が施入され、これを初めて演奏したのは琵琶法師であり、そ の音域的関係から、この調弦の乙の弦から上までの3弦の調律を、そのまゝ転用し、さ らに楽器構造改良の意見を加えながら、『本調子』『二上がり』などと、楽曲の作調に伴っ て改定していったものと、考えています。
果たせるかな、この各弦別音律譜表から、類推可能な転調音域の多様性は、譜例(6 3)の9種のほかに、次の譜例(65)の13種までに及び、合計22種と言う数にま で達してしまいます。前例に倣って各自に解析を反芻してみてください。
[譜例・65]