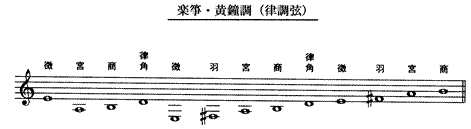(C)平調の律調弦
平調の律とは、平調(E)を第一核音とする律旋五音階に(E、Fis、A、H、Cis、E)、 派生音として嬰商(G)と嬰羽(D)が付加された、所謂五音七声のことです。また今 日の雅楽管弦曲の曲調の代表的なものとも言われています。
〔譜例・54〕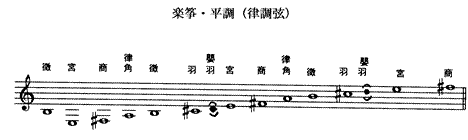
楽筝・平調(律調弦)
譜例(54)の楽筝の調弦譜表のなかの、黒符頭の2律は、派生音の嬰羽(D)に当た るもので、なぜか嬰商(G)に当たる音の指定はありません。従って五音七声は調弦上で は成立していないと言って良いでしょう。そしてこの二つの黒符頭の嬰羽は、その前の 白符頭(Cis)を、押手と言うテンションを上げる技法で、演奏することになっています。 或いは発音の前楽章の終わりに柱をずらして1律(半音)上げておく手法を用いたりし ます。嬰商もまた商(Fis)の弦を前述の操作によって、行うことになっておりますが、 3の弦のように低音の商は、弦調の関係から押手には厳しい問題があり、必要の場合は 柱移しを用いるべきでしょう。
それではこの平調の律調弦音列のなかに複合的に内在する曲調を考察してみます。
[譜例・55] 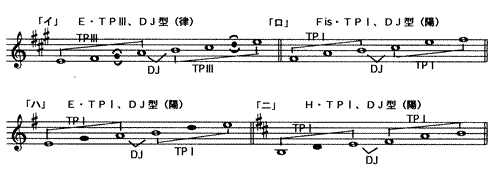
譜例(イ)は、平調の律旋音階の解析譜図です。そして当然その重属音(D)の、Fis を第一核音とする陽旋五音階〔譜例(ロ)〕が成立します。
また調弦法の中に、嬰商の指定がないことは、嬰羽だけの派生によって、その音列式 の組み替えがどのように成り立って、転調がなされるかを、体験的に示したものが譜例 の(ニ)で、Hを第一核音とする陽旋の五音階です。そして嬰羽が派生した場合は当然 の事ながら同主音転調による譜例(ハ)の、Eを第一核音とする平調陽旋の五音階です。
これらの派生音を旋律的曲趣として発生せざるを得なかったと言う、声律的感性とし ての思考に立てば、その曲部の普遍的整合性を得るために、上行式の嬰商・嬰羽の発生 と、下行式の商と羽の移行として、単なる旋律論だけで納得してしまっていることは、や がて複音楽としての楽理の思考停止となって、日本楽理の悲劇を呼んでいる、とも言え ます。いま一度改めて申し上げて置きますが、五音階以外の派生2音は、旋律的都合ば かりではなく、慣例律的曲調の推移による、その派生曲部の支配的音列の転換で、多重 共通音転調だと言うことを、忘れないでいただきたいものです。
続いて同調に対応する、楽琵琶の調弦法と、その各弦の音律譜表を検討することにし ます。
[譜例・56]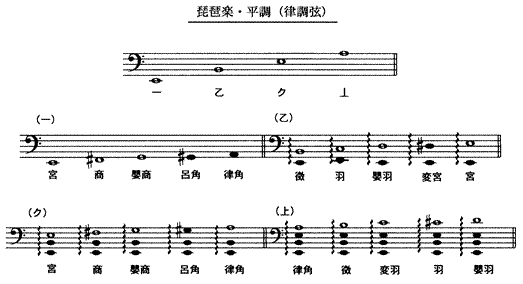
琵琶楽・平調(律調弦)
さてこの調弦法は、これまでの2種の呂の調弦法とは、一段と差異を感じられます。壱 越呂の場合の乙とク、そして双調呂の場合の一と乙との2弦間の音程が長二度と接近し ていたのに比べ、平調の律調弦では一と乙の音程が完全五度、乙とクそしてクと上の音程がそれぞれ完全四度となっており、三味線の基本的調弦律に著しく近いことです。
つまり呂の調弦に設定される長二度音程は、同調号平行曲調の旋律のDJ部分の、do , re に当たる部分となっています。そして音律機能的には、その旋律音階内の第二、 第三核音に当たるわけです。洋楽の7度の転回した密集和音は、上音が根音であり支配 力を持っていますが、呂調弦で生ずる長二度の密集和音は、下音の方が支配力が強いわ けです。このことはまた、呂旋と言いながら旋律音階の機能音列的支配を持っている、多 調性の特質とも考えられます。この点は実楽解析のところで、さらに深めてみたいと思 います。
次は各弦の音律譜表に目を移してください。一の弦の3の柱と、クの弦の3の柱に呂 角(gis )があり、楽筝の調弦では不可能な同主音呂旋も対応できることが判ります。当 然のことながら譜例(55)の4種の曲調のほかに、譜例(57)の2種の陰旋、8種 の曲調にまで、その転調域を拡大させることが出来ます。改めてまた各弦の音律譜表と 照合しながら、譜例(57)の各音階を反芻してみて下さい。この繰り返し学習は、将 来実楽を採譜し、その旋律的音列のなかから曲調を識別するための力を養うことになり ます。
[譜例・57]