5.五音七声の調性的関係
当然ここでは、付加音2声と単純五音階との調性的支配関係についてを中心に、論証 を進めるわけですが、その前に、従来の専門書などの付加音解釈が常識として定着し、今 日では歴史的権威となって潜在的に呪縛し、本当の科学的理解の妨げとなって、東洋楽 理としての思考停止状況を招いています。そこで付加音に関する歴史的解釈の概要から、 改めて検討を加えることにしました。
《三分損益法の手法で顕出された5番目までの音律を整理した音列式を、呂旋法または 呂の五音階と名付け、この階梯の2番目の角と徴の間と、5番目の羽と甲宮の間が空き すぎる(短3度音程)ので、次に顕出された6番目、7番目の音律をここに充当して、変 徴、変宮とした》と言った要旨のものです。これは五音と七声を成立させた手法の説明 であって、只単に音列の隙間を埋めただけの事です。なぜそれならば七音階と言わずに、 五音七声と呼んでレトリックを二分したかについては、なんの説明もされていないので す。これが楽理として最も曖昧なところであり、二千数百年と言う長い間、このことが 黙視されて来たわけです。わずかに音楽体験的な説明を上げれば、<上行の羽と下行の変羽>と言った説明が明治以後洋楽理論の伝来にともなって、上行の短調下行の自然的 短音階と言う洋楽理論の転用として、律音階上になされた程度のものです。しかしこれ とて単音楽的論承と言った程度のものと言うほかはなく、楽理的本質の進展はなに一つ 見られなかったものです。つまり五音階と付加2声との調性感が欠如していたのです。 従って五音七声の名称的動機は五音階が中心の調性で、付加2声は音階外の旋律的派生 音と考えられるものだったのではないかと言うことです。
音響楽的には当然の事なのですが音響楽理が体系化されていない時代に三分損益法の6 番7番目の音律が、先顕の五音階の隙間に、うまい具合に充当されたものです。筆者に は、この整合性を無視することが出来なかったのです。しかもこれらの付加音は、実際 の奏楽現場では、旋律的に隣接の五音階の音律と連繋して派生することは、殆どといっ てよいほど無いのです。特に上下する旋律進行の過程では、上隣接の音律(核音)を飛 び越す場合が多く、こうした傾向は創造的な一時的転調ではないかと考え、様々な移調 を試行するうちに、大切な基本的実態を見落としていたことに気づいたのです。
つまり十二律顕出の過程で、6番7番と言うことは、2番3番と同様の損一益一を各 一回づつの音律を求めたということです。言葉を換えれば完全五度の上の音(属音)に、 更にその属音を求めたと言う、音階支配機能の移動ではなかろうか、所謂二重属音 (Doppel dominante) とも言うことが出来ます。これはまさに異名同音転調と見立てた 側面から類推すれば、旋律動機的一時転調による派生音と言う指向で、何とかなりそう だと言う気がしてならなくなってきたのです。〔譜例「32」参照〕
[譜例・32] 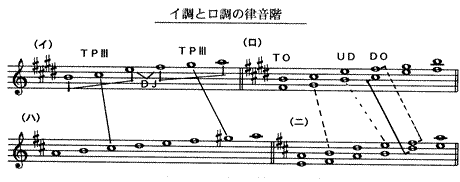
筆者が早速長二度上の二重属音的遠隔音から、律の五音階を立てて見たのが譜例(3 2)の(イ)です。言うまでもなくこれは、h' を第一核音とする律音階です。
その下段の譜例の(ハ)は基本的律音階で上下を照合しながら付加音2声と五音階と の関係性を、考察する扶けとしたものです。続く譜例(ロ)と(ニ)は、2声下和音構 成となった両者で、同じく照合解析用の対照音列です。
先ず(イ)と(ハ)を照合して推測できたことは、基本的律音階である(ハ)の2声 付加音は、(イ)の移調律音階上の二つの中間音と言うことです。そしてその2声のすぐ 下の第一核音 h' と第三核音 f''is が(ハ)の第一、第二中間音で、明らかにこれは支配的核音機能の転換が浮き彫りにされてきました。
こうした解析経緯を矢印線と点線で結んで見たものが、即ち(イ)と(ハ)を結んだ 対照譜図です。特に点線で結ばれた両者の共通音 h' と f'' is は、これらの音を軸として旋律的転調が果たされるもので、さらに中間部の e'' は両者の第二核音と第三核音と言う、支配的音律同志である関係から、異名同音としての転調軸の役割は最も 大きく、その効果は理想的ということが出来ます。しかし単音楽の旋律志向の場合は、こ うした解析法は余り神経質になる必要はなさそうですが、器楽的複音楽の立場からはけっ して等閑視は許されないことです。
何と言っても、東アジアの五音階の上の複音楽では、転調意識がその音楽性を問われ る鍵である証拠として、次なる譜例(ロ)と(ニ)の対照譜図に従って、その考察を深 めてみることにしましょう。
旋律的三つの共通音下の2声和音は、その音列構造の関係から(ニ)の第二核音に当 たる d'' が(ロ)の c'' is に移行していることに注意してください。つまりこれは五音階音楽の2声進行には、同一調性進行の中には3度音程部分が一ケ所、3声進行 の場合には二ケ所しかあり得ない、と言うことを意味しているのです。前にも述べた通 り東アジアの五音階音楽では、和声的3度音程の部位が調性を決定する第一の鍵と言う ことは、即ちこのことだったのです。
それでは実際の楽曲の場合には、こうした派生的付加音がどのような状況で現われる ものか、そしてこれまで論証してきた転調的調性感が楽曲進行の上から何を意味してい るのか、改めて実楽の上から検討してみることにします。次の譜例(33)は、漢の宴 楽に淵源を持つと伝えられ、現在でも京劇音曲などでよく用いられる律旋楽曲の一部で す。
[譜例・33]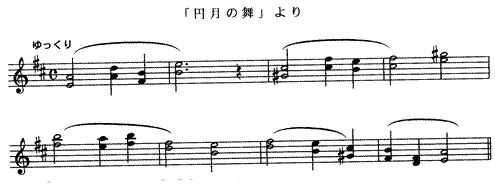
譜例(33)の楽曲の加声(二部)部は、筆者が付けたものです。実際には最高音部 に笙の合竹が通奏されていたようですが、現在では高音の笛が偶発的変奏(Heterophony )方式で奏されているようです。
ともあれこの旋律にしたがって、七音階論としての立場からは、洋楽的六度三度の2 声進行も可能ですし、結論として上記の2声進行に最も自然さと、整合性が感じられた ところから、参考までに上記様式の2声進行とした次第です。
譜表上部の点線括弧部分は、Hの律旋に転調された楽節部分を示したものです。更に 符下に印された丸はAとH両調の共通2声和音を示したものです。
特に4小節目の両調の3度平行が発生しても、別におかしくはありませんが、そうな ると軸を持たない突然の転調となってしまい、進行上の前後の関係から、その違和感だ けが際立ってしまいます。
軸を持たない転調は、4度や5度の跳躍旋律以外は避けたほうが無難でしょう。従って平行三度進行は五音階音楽の場合はあり得ないと結論することが出来ます。