4.五音階音楽の和声的展開
次の譜例(28)は、基本的呂旋法の上複合音程を加えた音列式です。
[譜例・28]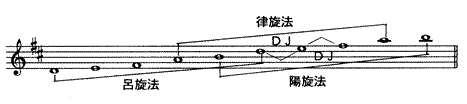
そしてこの中音域にdo からDJされたTP�の律音階。re から同じくDJされたTP�の陽音階。さらにその下音域にCJ(a’)された d ' 〜 d " まで の呂旋法が存在する。その位置的関係を示したものです。
従って中央の律音階を中心に加声を試みることによって、そのままの形式で上下に延 長して加声的類推が可能なわけで、陽音階や呂旋法の音列上にも、全くそのまま対応で きるわけです。
次の譜例(29)は、律音階に2声による旋律的下二和音を試みたものです。
[譜例・29]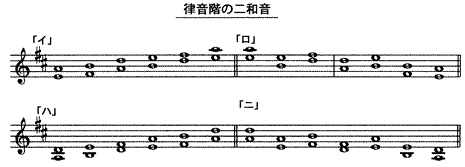
譜例(29)の(イ)は、律音階の各音に1音間隔下の階音を併行させた、併行旋律 音列式を加えたものです。その自然な2声の流れを幾度となく奏楽体験の上で確認して 頂きたいものです。またさらに主旋律音列(上部)と加声音列(下部)とを別々に奏しながら、両者がそれぞれに独立した旋律感を備えていることも確かめてください。しか もまた併行2声を同時に奏してみても、両者は全く相克することなく、響鳴上の混乱も なくむしろ上声部の旋律が際立っていることも見逃すことが出来ません。こうした音空 間は自然的協和の移行と言うことが出来るでしょう。
これはまた2声相対の響態と言うべき現象です。何でもないようでいて、音響楽的に は重要な意義が秘められているものなのです。洋楽の併行2部は3度や6度の音程を主 軸として構成されていますが、加声部進行がどうしても旋律的性格に乏しく、しかも同 時進行の場合には、音量的調整を必要とします。ひとつには平均律複音楽の弱点とも言 われているものです。ところがこの漢の五音階音楽を平均律楽器で演奏してみても、全 く3度6度2部のような傾向はありません。つまり響鳴状況が揺れ動いて、必要な音律 状況に立ち上がって聞こえて来るようです。この不思議な実態を皆さんにも、是非とも 実験の上確認していただきたいものです。勿論それは筝や三味線さらに尺八の様な邦楽 器旋律と、ピアノとのユニゾンと言うことではありません。例えば旋律と和声部そして リズムと言った各受け持ちセクションを複音楽的に対応されれば、全く差しつかえない と言うことです。
但しその場合は、本講の標榜する東アジア五音階に対して、下和音的展開の編曲に よる以外は、現在のところ無理かも知れません。また総て平均律楽器であっても、少し の問題もなく、むしろ理想的音空間の創造につながるようにも思われます。
さて続く(ロ)は五音階音楽の特徴とも言える下行的跳躍旋律に対しての加声2部で す。これも譜例の(ハ)と合わせて、幾度も試聴していただきたいと思います。特に音 階上第五音の f " is と d'' ( mi とdo ) の長三度の存在は、調性感を司る鍵とも言えるほどに、なかなか整然として自然でしかも、味わい深い併行協和進行を感じさせ ます。
いずれにしても、従来の常識的上和音を試みずして、下和音の適合性を評価すること は早計です。従って参考までに本来の上和音を構成してみたのが譜例の(ハ)です。こ れも下和音の場合と同様に、1音間隔の2声音列式です。
これもまた性格的には自然な流れと言えます、そしてこの上声部をよく見れば、基本 的呂旋の音列構造となっています。つまり際立ってなければならない旋律が、呂旋法の 下和音列となってしまった、と言うことが出来ます。
従って両者はそれぞれ独立してはいながら、同時進行するとなんとしても呂旋法的支 配が強く、その終止感はなんとしても不完全性で中間終止形なことにお気づきでしょう。
譜例の(ニ)は、(ロ)と同様の下行跳躍旋律ですが、(ニ)の主旋律(下声部)が沈 滞してしまっています。これは律音階と言う曲調の上から見て、見捨てられない問題点 です。こうしてみると確かに下和音進行の方が、安定感もあり、曲調的混乱も少ないと いうことが解かります。
これまでに確認した事柄を踏まえて、次なる下和音進行に移ることにします。
[譜例・30]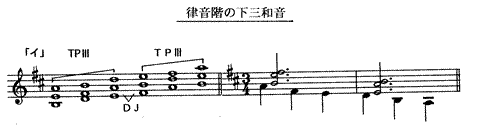
律音階の下三和音
譜例(30)の(イ)は加声部第2音の下に、さらに1音間隔の第3音を加えた三声 律音階です。当然この加声法式から発生する和音構造の変化は、大変興味ある現象なの です。つまりTP両端の核音のところは、四度七度略して四七の和音構造で、これは基 本的和音の型と言えるものですが、中間経過音 mi (f' is)と la(h')の下にはそれぞれD dur の 四六の和音と、H moll の三六の和音構造となり、7度和音の中間に六度和音が挟まって、3声TPを形成してDJされている事がわかります。
そして六度和音の両者は、基本的律音階の記譜上の調号でもあるニ長調の併行調、D dur, H moll 両調の主和音です。しかも第一転回型と第二転回型と言う顕れ方は、将 来低音部進行を創造する場合、編曲上の洋楽のそれとは大きな違いを生ずる本質的要因 ともなっているものです。
またこれらの3声進行の中にあって、経過的にせよ長短調(Durmoll )的複調音楽としての感覚から、四七の和音と言う終止音で解決することが東アジア複音楽の特質でも あります。
さらに陽旋音階の場合は、その音列構造の性質から、四六・三六の和音のところが核 音に当たるところから、長短調という複調感はより一層色濃く感じられるわけです。
ここで特に注意を要することは、基本的下三和音の併進行、中音部までの場合に限る と言うことです。器楽編成の都合上低音部さらに重低音部が必要となった場合、第三音 だけの主旋律との併行進行は、並行二度の連続が旋律進行に対する相克効果となって、響 態としては全く逆の結果を生んでしまいます。従って通常の3声和音の第3音は上に転 回されて、譜例(ロ)の様な最高音部の通奏的和音様式とされています。特に転回様式 から生まれた密集和音は、リズム和音としても最も理想的と思われます。また全体的和 声進行の中に、平行五度が発生しても、東アジアの五音階音楽の場合は洋楽のそれとは 違って全く差し支えないことなのです。
ともかくこれまでのところ、極めて概念的ながらも続けて下4声和音までの検討を加 えておいてから、実楽の本格的解析に移ることにします。
なんと言っても雅楽の最高音部を受け持つ、笙の合竹には4声和音構造が多く、それ らの殆どは4声和音の第三音省略型や、複合多声音が多いように思われます。
[譜例・31]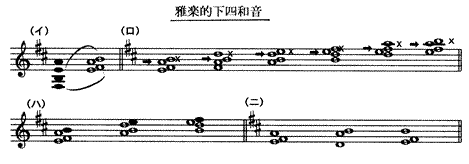
雅楽的下四和音
先ず譜例(31)の(イ)の黒符頭による縦型音列は4声和音の基本型です。多編成 の器楽曲の場合には、この構造式のままの平行進行として、大変効果を上げることもありますが、通常の4声和音は矢印線のように、第二転回型の密集和音として用いられる ことが多く、それが(イ)の白符頭の4声和音です。
次の譜例の(ロ)は律音階上の4声音列で、矢印はその根音として、X印は省略され ることの多い第三音を示したものです。
そしてこれらの和音相互に隣接する和音との関連性を照合し、更なる検討を加えてく ださい。必ず相互に2音以上の共通音を持っています。従ってこれらの共通音を持続も しくは省略し、旋律音との対応を加味すれば、譜例(ハ)の3種類に絞っても、充分に 旋律進行に対する和声支配をカバー出来るわけです。さらにこの3種類の和音の持つそ れぞれの核音的支配機能を考慮に入れて、いま仮に調性的和音機能名を与えれば、主和 音(TO)、属和音(DO)、下属和音(UD)と言うことになるでしょう。
続く譜例の(ニ)は、これら調性的4声三和音の構造が、最も自然な無理のない進行 で次なる和音に推移できるように、整理された奏楽状況型の省略和音型ですが、楽曲的 流れの状況に対応しては、その第4音を省略する場合もあるように思われます。
いずれにしても、単純五音階音楽の場合ならば、これまでに修得した基礎的知見で楽 曲解析には事欠くことは無いと思われますが、付加2声が派生して五音七声ともなれば、 とくに派生音前後の和声的進行に響態的違和感は否めません。従来の旋律的派生音に対 する解釈は単音楽志向が中心で、複音楽的意識で受け止めると極めて曖昧なものとなっ てしまいます。現代的多声器楽曲の立場から見て、何としてもこの不自然さは我慢でき ないものです。
只単に伝統的前例と言った理由だけから、曖昧さをそのまま踏襲するわけにはいかな いと、筆者はここに強く申し上げておきたいのです。
そこでこの際、是非とも五音階と付加音2声との関係性を、調性科学の上から釈然と させておく必要が感じられますので、基礎楽理修得の現状としては、多少難解な向きも あろうかとも思われますが、せめてその概要だけでも検討を加えておくことにします。