6.六律六呂と六調子
わが日本列島では、漸くにして古墳時代を迎えようとしている頃、漢の長安では式典 奏楽の最盛期に入り、かくて驚くべき単一の倍音律を完成し、その音列から十二律を確 立し、さらに多様な五音七声という旋律指向の音組織まで制定していたのです。
現代のような日常をニューメディアにカバーされた、地球規模の時空理念からは想像 することの出来ない古代的感性と精緻な音律と言ったアンバランスに、戸惑いを覚えて 当然かも知れません。ところが古代漢民族の知識人達の間には、三分損益法や十二律の 作定、そして五音七声の配立も、日常的営為の中から発想して然るべき共通理念と摂理 に基いた土壌があったのです。
つまりそれが易学からの陰陽思想だったのです。《書経・周官》には、「陰陽を燮理す」 とあるように、最高権力者たる者の心得の第一に、天地四時の道をやわらげ治めること によって、その政道よろしきを得れば、自ら天地がこれに感応して陰陽が整ってくると 言う政道即自然観のことでしょう。ここで言う陰陽とは、五行説の事と思われます。
五行とは、土を中間に立てて木と火は陽、金と水は陰と位置付け、これらの消長に対 応して、天地の異変や災祥、人事の吉凶などを説き明かすものと言われています。この 易法がわが朝に伝わって、陰陽道(又はオンミョウドウ)と呼ばれているものです。
長安の官人たる者の不可欠な教養の主軸が陰陽法に通達していることでした。そして 仕官や私的日常の行住座臥一切に、この法に則る事が求められ、また自らもそれを望ん でいたと言ってよいものでした。こうした社会通念は長い歴史的感性の奥底に根差して、 すでに漢民族独特な思想となって、公私にわたる日々夜々の四威儀を支配していたわけ で、この認識を前提にせずして漢民族の古代社会は論ずることは全く出来ません。
もう少し解り易くすれば、陰陽と言う相反する二種の気は森羅万象の悉くの化成の要 因となるもので、現代的にその実在性を表現すれば、電気や磁気の陰極と陽極に当たる ようなものです。それは易で謂うところの相反説の吉凶とは全く違ったものであること も確かと言えます。この両極はいづれかに偏ったり、またどちらも忌み嫌うべきもので もなく、つまり調和のとれた陰陽の二気の和合こそ、万物を造化し創成する基因だと考 えられていたのです。
従って笙のように、その最高音部を掌る多声構造の響態も、ただ単に聴覚的感覚から 生み出されたものではなく、陰陽二気の和合を積み重ね、最も旋律と調和のとれた多声 を以て尊しとしていたようです。
例えば奇数値振動数(陽)の或る基音から、三分損一によって顕出された音は、偶数 値振動数(陰)となり、さらにその音から三分益一によって求められた音は、奇数値振 動数(陽)となると言った具合で、その作法の根底に流れている思想は、陰陽和合の定 則性に暗合していると言えます。つまり2対3とか、3対4とか言った弦長の対比法は、 物理的と言うより陰陽の摂理だったとした見方は、時代性に適ったった忖度と言えましょ う。そしてここに至って思い当たることは、前章に提起した太陰暦との不可思議な整合 性も、自ら氷解して来ると思います。
果たせるかな長安では、十二律制定後間もなく各段の音律に陰陽の位置付けがなされ たのです。すなわち第1段黄鐘を陽の音調として、第2段の大呂が陰、以下順次交代に
陰陽を当てていきました。そして陽の音調を宮とする音階には律旋を陰の音調宮には呂旋を立てて、これを六律・六呂と称別によって位置付けたのです。
〔図の(8)参照〕
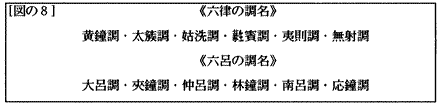
こうして漢の長安の式楽の中に定着した六律・六呂は陰陽調和の摂理の理念から発想し たものであり、楽理的な根拠とはなんの関係もないことがわかったわけです。
わが朝に伝来した長安の奏楽は、宴楽(中国の俗楽)が主体で、しかも律の2調子と 呂の4調子でこれを総合して六調子と呼ばれている調性ですが、こちらの方は当然理念
なき調性と言えます。さらに楽理的には、なんの意味を持っていないと言えます。
〔図の (9)参照〕
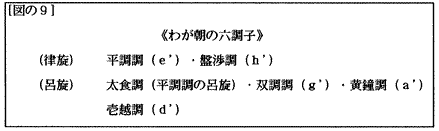
なおこのほかに別格として、狛壱越調とよばれるものもありますが、これは非常に太 食調に近いものと言われています。明らかに古代朝鮮半島のもので、使用する楽器の関 係によるものと思われます。
ともあれ古代中国は、楽器的音楽文化圏と言われ、これと対照的に我が国は、歌謡的 声曲文化圏と言うことが出来ます。
従って楽器伴奏だけの 楽の曲種の中に、辛うじて純粋音楽としての呂旋の名を止め、 声曲的慣例律に適合した律旋音階が、様々に進化し陽旋・陰旋の五音階音楽を派生した ようです。特に中世の前半から雅楽様式の中に、歌曲(または歌物)という曲種に加え られ、我が国古来の固有声曲と外来奏楽との習合による、国際音楽時代を迎えることに なったわけです。それが『催馬楽』や『雅楽朗詠』となって、国風に傾いて開花し、多 様な展開を見せていったと言えましょう。
特に歌曲発生に先んじて、833年仁明天皇の即位の式典の中で演じられた管弦奏楽 は、『越天楽』と呼ばれ、 楽から独立した純粋器楽であり、わが国において進化した特 有の雅楽管弦の嚆失とされています。
やがてこの雅楽管弦に固有の声曲が加わって、三十八曲に及ぶ歌曲へと展開し、これ が国風化の新古代から中世の初めにかけて、演奏の機会がいかに多かったか、文献の上 から拾ってみれば『鳥破』『鳥急』『万歳楽』『賀殿急』『五常楽急』『三台塩急』『甘州』『春 鴬囀』などが上げられます。これらの曲名の後に「急」と付いたものが多いのは、中世 以後の我が国の雅楽曲のほか、一切の表現文化の上にもたらされた形式的風潮で、序・ 破・急と謂う流動的移行様式で、それは構造的様式美と言う価値観として、国風思想の 基本的手法となって定着したものです。
つまり奏楽の場合の発想の手段として、作調、編曲さらに旋律的動機にまで及び、曲 態としては序・破・急と言う三部楽章形式の表現的流れを意味し、急とはその第三楽章 の盛り上り、そしてテンポの急速性を兼備した終曲部のみの単独の演奏のことです。従っ て急の付いてない曲名は、当然のことながら序・破・急三部形式でまとまった全曲の奏楽を意味していたことと思われます。
しかもこれらの歌曲は、すべて旋律が中心となっていたのです。ここで現在カナダの 音楽社会学者として高名なW.シェーファーの発言を借りれば、「音は人間の聞く行為を もって、はじめて成立する」。かって漢の長安で改定された旋律の基本的音階も、所詮そ れは陰陽摂理の上に立てられた、音列的組み替えだったわけで、わが朝に渡って演奏の 機会が多くなるに伴って、その不自然さ、不適合性は、人の聞く行為のうちに覚知され、 伝来の律旋音階の付加音変宮と律角の1段下の角、それぞれのさらに1段下に嬰商と嬰 羽を配立して雅楽朗詠のような本格的歌詠ものには、特に大きな効果を上げ、こうした 音楽的対応が、今日の邦楽的曲調に著しく影響を及ぼしていると言えます。
なんと言っても中世の国風思想は、貴族階層の私的生活にまで投影し、その素養の第 一として音楽の遊びが発生し、家庭的管弦合奏の風潮へと波及したのです。
とき恰も、源 博雅と言う横笛や笙などの名人が出現し奏楽の普及と《楽房》を撰し、そ の指導と共に芸道思想の興隆に大いなる貢献を果たしたと言われています。
従って博雅の名は、我が国固有の旋法論と共に不滅のものとなっているわけです。彼 の愛用の笛の管音が壱越だったところから、尺八で言えば尺八寸、その音階論は壱越調 を基調として、律旋を中心に多様な付加音を考案し、今日我が国に遺在する4種類の五 音階論の基本的役割を果たしていると言っても良いものだったのです。
いま一度ここで改めて、譜表の上から中国の五音七声と我が国で変化した音列を比較 して確認しておくことにします。
[譜例・11]
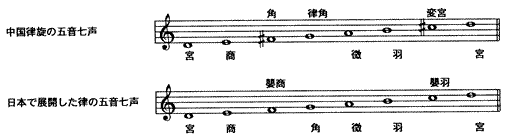
譜例(11)下段の五音七声に特にご注意ください。実はこの音列の中には、現在我 が国の各地で歌われている律旋、陽旋、陰旋、そして沖縄陰旋までの総てを含んだ多調 性と言う複合音列となっています。
中世という我が国の楽理状況は、自然的曲調としての解析は、なされよう筈もなかっ た音楽社会だったといえます。この複合音列の中から、後世の俗楽の基調的4種の五音 階(pentatonic scale)は、当然知る由もなかった訳です。それにしてもこの音列の 嬰羽に当たるc″をサブ転回してc′に置けば、現代音楽の基本的自然音階(natural scale) 、つまりピアノの白鍵だけの七音階(musical scale)が成立します。これは又後の項で詳しく説明をするとして、この七音階からどのような類推を通して、3種の 音階を解析すべきか、一見して即答出来れば、すでに本講の基礎編は卒業したも同然と 言えます。
ともあれ鍵盤楽器の存在しなかった我が国の中世にあって、自然音階を類推させる音 列を編み出していた源 博雅をして、日本のバッハとまで言わしめるその要因は壱越調の旋律音階に嬰商、嬰羽を付加して、国風の曲調に対応させたところにあったわけです。
だがしかし、音楽美学とは別次元の理念、古代中国からの陰陽摂理の階音名の踏襲を 墨守したことが、またそうした理念的制肘を離れることが出来なかったことも、歴史的 国民感情と言う宿命的弱点とも言える訳です。それは明治以後の日本音楽研究諸賢の中 にも屡々見受けられる傾向でもあります。
さてここで、ひとつの提案をさせて頂きたいと思います。残念ながら今日の中国大陸 では、漢の長安の十二律奏楽の確かな実態は全く湮滅してしまったのです。台南の孔子 廟の式楽と韓国の国学院の王宮式楽、そして我が国宮内庁楽部に、その延長線の奏楽実 態として辛くも遺存するのみとなってしまったのです。従って奏楽実態としての解析は 資料的確実性の上から、我が国宮内庁の雅楽部の曲種を中心に行う以外には考えられな い現状です。
しかしその際の用語について、楽理的将来への展開のためにその用語の淵源とする環 境が、漢の長安の宮廷と言う特質性からの弱点ともなってる論理的韜晦性は否めません。 本格的楽理以前の往時は、それなりの役割を果たし、わが朝の楽人たちに寄与するとこ ろは大きかったと言えますが、今日の世界的音楽理論としての側面からすれば、楽理的 というより今や文芸的伝承と言わざるを得ません。
その原因の一つとして、用語的動機性と言う問題も考えられます。そしてその第二に は歴史的成り行きとして《楽書要録》を中心とするその周辺の文献から、当然のことな がら縦書き文化論を、横書き音楽空間論に移行する際の軋みが上げられます。そしてそ の第三には古代の二つの社会の二つの理念の相違と、それを更に現代の楽理意識で汲み 取ろうとする多次元的二重三重の翻刻からくる煩瑣性による不解明感だったと言えます。 このままでは余りにも意識伝達の媒体が曖昧で、思考停止で盲信するほかはないと言っ た先人の轍を踏む恐れ無しとしません。
これまで長々と繰り返してきた古代の音楽的資料からの考察は、概念的と位置づけそ れでよしとしておきたいのです。
そして前述の宮内庁雅楽を通して得た普遍性を三味線声曲を中心とする俗楽類一般の 実態に照らすことから、その資料的音源になんの不足がありましょう。
わが国固有の伝統音楽界の、過去から現在は、否定も肯定も出来ない実態とすれば、現 在から未来はそのままで良いとは誰が言い切れましょう。これまで多少でも明らかとなっ た結果として見えてきた結論や、楽理として考えられてきた様々な論証は、全く別次元 からの知性的導入であったり、奏楽現場での手法等は感覚的選択の積み重ねであった訳 です。
「理論は名曲ではない」筆者の脳裏にはいつもこの言葉が走り抜けます。「しかし名曲 は最も理論的である」と、このパラドックスからの教えは、有給の歴史的価値観のなか に支えられてきた、楽理無き音楽の理論性の確認の無い限り、未来への展開は危ぶまれ るとしか思えません。極言すれば砂漠の川とはなりかねないと何を根拠として言えるで しょうか。
洋楽が今日のような進化を果たすまでには、幾つかの大きなエポックがあったと言わ れています。
なんと言ってもそれは、ルネサンス期と古典派の中間に挿まれた、十七世紀から十八世紀のバロック時代に、単音楽(monophony )と複音楽(polyphony )の競合の課程で、ドイツ大学楽派の間では、《古代ギリシャ音階論》の研究が盛んとなり、調性音楽に対す る重要性が再確認されたことでしょう、
そしてそれ以前の十五世紀から十六世紀にかけて、すっかり定着していた基本的全音階 論までに展開し、改めて改めて音階の持つ機能性を闡明にしたことが、現代音楽までの 原動力となったとも言われています。
古代ギリシャの音階論は、漢代の三分損益法の原理となぜか相通じるものが感じられ ます。本講はここでひと先ず西洋の十七、十八世紀に眼を転じ、当時の至純な楽理的姿 勢を通して、改めて東アジアの五音七声を再考してみることにします。