4.十二律の制定と五音七声の配立
それでは前章で修得した三分損益法に従って、二千百有余年と言う遥かなる時を超越した音響楽理的思考体験の実践に移ることにします。
先ず古代中国の奏楽の音律の基準と言うか、楽器編成様式の中心的役割を果たしてい たのは前出の編鐘の中の黄鐘と呼ばれた鐘の音律だったようです。そしてそれをそのま ま起音(基音)の音名として、黄鐘と名ずけたわけで、まさにこれが音律の基本的実音 名で、世界で最初の実音名だったと言うことができます。
今日我が国に遺存する最古の律管の基音である壱越が、この音律に当たると言われて います。
かって専門関係者たちの立会いのもと一度だけ試聴会が行われた際の報告によれば、現 代の国際的実音のd’(Standerd pitch d’)より80分の76だけだけ低いものと言われています。所謂東洋的微分音とは言われながらも、極めてd’(Eingestrichen d’)に近いものなので、本講の譜表ではd’、つまり五線(高音部)の第1線下の下第1間に 記す事にします。
さて漢の京坊では顕音作業の前に、当然の事ながら顕音用の弦鳴器具を多数製作した ように思われます。〔図の(4)参照〕
[図の4]
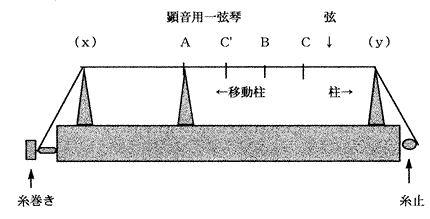
図の4の両側に立てられた柱(X,Y)は固定させ、その他に移動柱を用意して、所謂 移動柱を一つ持つ一弦琴のようなものです。X,Yの長さの三分の一の位置A点に移動柱を 立てた音律が黄鐘となるように調弦をしておきます。
当然の事ながら弦が発音される際の、各ポイントのテンションを損なわないために移 動柱と弦の接点には微かな隙間があり、その弦との接点の真上に軽く左中指の腹部で押 えたまま、右人指し指の爪先で弾いて発音させます。これが第一作法の技術的ポイント だったと言えます。
そしてその第二作法として三分損一です。A〜Yの弦長の三分の一の位置B点まで柱 を移動させ、第一作法同様の技法で顕音し、その音律に同調した鐘の名を転称して、林 鐘という実音名を与えた。つまり同時代的表現としては黄鐘から三分損一して林鐘を求 めたと言うことです。
さらに次ぎの第三作法は三分益一です。B〜Yの弦長の三分の一位置C点を求め、B 〜Cと同一の長さを逆行させたC’点で顕わした音律に太簇と名ずけたのです。これも また編鐘の中から同音律名の転称だったのです。
以下は、これまでに定められた音名、黄鐘、林鐘、太簇に対し、その顕出順に1、2、 3と言うナンバーを付記し、顕音弦域だけを下の図の(5)に拡大して図面上の解析を 続けてみてください。
[図の5]
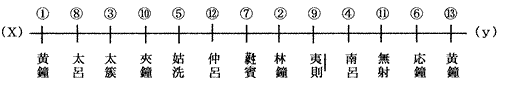
さてその第四作法は、太簇�Bから三分損一して南呂�Cを求め、これから三分益一して 姑洗�D、これから三分損一によって応鐘�Eを求め、この後は複合音程を避けるため、三 分損一を2回繰返し?賓�Fと大呂�Gを求めた訳です。
さらに�Gから続く第九作法は三分損一して夷則�H、これから三分益一して夾鐘�I、そこから三分損一して無射�J、続いて三分益一仲呂�K、こうして最後の第十三作法は三分 損一して甲の黄鐘に達した訳です。
そしてこのように顕出された音律の一つ一つは同時に竹製の中空に同調させ、その長 さの順に並べて組み合せ、基音の長い寸法から第1段、第2段と数値を上げた段名をつ け、音律の基準としての律管を完成させた、と言われています。
このように定則的に3分の一の増減と言う、単一または倍音律に従って顕出された音 律の中から、まず最初の基音黄鐘に宮という音階名を付け、次ぎの林鐘に徴、続く太簇 に商、そして4番目の南呂には羽、さらに5番目の姑洗には角などの名を付け、これを 下の音から整理した順に、宮商角徴羽の五音階を配立しさらに旋律音階としては角と徴、 羽と甲の宮との間が広く、不自然な処から、第6、第7の作法で顕出された応鐘とズイ賓 に対し、それぞれ変宮、変徴と言う付加階名を付けて7声としたと言われています。
世に謂う呂の五音七声とはこのように器楽的発想から人為的に構成されたもので、声 曲的慣例律からみて、全く別次元から配立された呂音階(本来は音列です)と言うこと が出来ます。
図の(6)は古代中国長安の教坊で定められた書式に従って、筆者が作図した十二律 名表対照表です。
〔図の6〕 十二律対照表
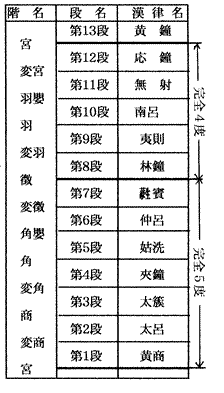
この十二律名対照表の上下にはそれぞれ複合音程としての十二律が二重になっていたと言われていますので、前記編鐘の音域同様の器楽的音域響態を窺う事が出来ます。
特に第1段.第8段そして第13段が太線になってい 、奏者たちにとっては多様な 側面から、音楽現場意識
を考察する上で、大変示唆に富んだものがあるわけで
す。第13段の黄鐘から第8段の林鐘までの音程は、
完全4度。その林鐘から第1段の黄鐘までの音程は、
完全5度。つまりこの間隔を律管の上で崩さず移動す
れば何処でも協和音程を得られるわけです。
合竹と呼ばれている笙の和声は、こうした手法から積
み重ねられたもので、その規準としての8段6段であ
り、音程上の完全5度.完全4度関係でもあるわけで
す。
そして《楽書要録》で表現された三分損益法を順八逆六法と言う手法は、損一の8段 累進が順八であり益一の6段後退が逆六という奏楽現場の実践的側面からの手法的表現 だった事が、見えてくるようです。〔譜例(7)参照〕
さらにこの数値的表現の順八逆六は、第2段の大呂を宮とすれば、第9段と第4段の 関係になって、手法として移行すればそのまま大呂調としての合竹が得られるわけです。
なお我が国の雅楽奏者の間でも楽理的発想を抜きにして、この手法用語は踏襲されて います。
さてこうして制定された漢の五音七声の階音名は、我が国の専門家達の間でも、全く意味を持たない名詞のように解釈されているところから、時として旋法上の解釈の際に は、階名としてどれに当たるかについて齟齬を生ずる事があり、このことが楽理的論証 のための大きな弊害となって、所謂《円周論的韜晦説》と評される要因ともなっていま す。
こうしたことは時代的用語に対する現代的自己投入であり、大変ナンセンスなことな のです。そこでここで改めて古代中国の識者達の音楽意識を、同時的感性に立ってその 階音名の意義と役割について考察を加え、その名称動機を概念的とは言え、一歩解明し ておきたいとおもいます。
つまり漢の五音七声の階音名は、流石に象形.会得文字のお国柄だけあって、無意味 な標音文字ではなく、確かな動機が内在していたようです。
例えば洋楽のシラブルネーム(Sylable name)の do と言う主音に対して、その上下に完全5度の sol (上)、 fa (下)には、調性的に切り離すことが出来ない近親音として、上属音(Dominant ),下属音(Subdominant)と言う機能名が付けられています. ところが中国の場合のシラブルネームは階音名であると同時に機能名としての謂が含ま れていたのです。