Ⅲ 壱越調 『武徳楽』
『武徳楽』の本来は、伎楽として笛の演奏だけで演伎を伴っていたものです。その後演技 は忘れられ、管楽部楽人達によって笛の曲として伝承されていたものが、雅楽管弦の楽 曲として作調編曲され、今日に伝えられたものと言われています。本節の課題となった 壱越調のほかに、管弦記録総譜の第三部のなかに、双調のものも伝えられていますが、基 本的曲調は壱越調とされています。そしてその調弦用の曲調としては、呂旋法と言うこ とになっていますが、これまでの解析体験を通して確認できたことは、呂旋法とは音律 構造上の基本的建て前であって、中国の古代に於いて徴調の律音階が発見されて以後、実 際の奏楽上の旋律進行の基調は、この音階機能のもとに支配されるものとなり、律音階 の母胎としての音列式であって、その支配的機能は有名無実となっていました。
従ってこの壱越調の呂と言う調号も、これを基層音列とする、黄鐘調の律音階(A・T P� s c a l e)がその主調と考えて、ほぼ間違いないものと思われます。しかもそれ が所謂、徴調の律と呼ばれた曲調そのものでもあります。
また本楽曲の沿革の側面から見ても、雅楽管弦の曲趣と曲態としては、最も古風を伝 えるものと見て、間違いありません。
さらに曲態の特質として律動的設定は小曲「早四拍子」となっています。これは能楽 で謂う、4種の器楽伴奏を形容する四拍子と違って、奏楽の速度と律動を意味したもの です。
前節の『越天楽』も、同様の設定がなされていますがこれは近古代までの速度感覚から 見た表現で、こんにちの andante に近いゆったりとした四拍子と見るべきでしょう。
そして四拍子という継起的律動様式は、現代音楽で謂う拍節的リズム、定型アクセン トのそれではなく、定量的単位の4呼間ごとに一楽詞とした、確認を意味するかまたは それを促す、体鳴か膜鳴楽器を打って、進行速度の調整を図る手法のことです。つまり 楽曲的流れの節目に対する規定を、示した用語と見るべきものです。
それでは先ず、課題曲の『武徳楽』の旋律楽部を代表する龍笛の全使用音域表から検 討を加えることにしましょう。
[譜例・145]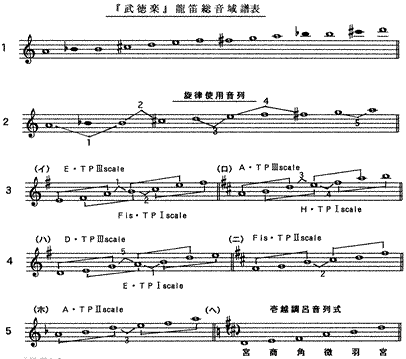
『 武 徳 楽 』 龍 笛 総 音 域 譜表
譜例(145)の一段目が『武徳楽』の龍笛総音域譜表です。中間の経過音的黒符頭 を含んだ、この複合音列を整理した使用音列式が二段目になります。その5カ所の鍵で 結んだ部分が、DJとして成立する可能性を持った長二度間隔の部分で、1から5まで のナンバーは類推順位と五音階検索の次第を、照合する場合の参考としたものです。
そしてそれら各部位から上下延長音列上に適合する五音階が、その次下、三段目以下 の(イ)から(ホ)までの各曲調です。さらに五段目の(ヘ)は(ロ)のA・TP�scale の下降延長音列上に、伝統的に指定された、壱越調の呂の音列式も含まれていることを、 参考までに示しておきました。
ともあれ、この(イ)から(ホ)までの5種の音列のなかに、計8種類の曲調が存在 し、これらの集合された音列式が二段目の音列式だったわけです。従って楽曲『武徳楽』 は、当面のところ上記8種類以外の曲調は、旋律進行上には存在し得ないと、考えられ た次第です。続いてこれらの曲調の推移と併行する、合竹の評価を検索するために、類 推音階別にその下和音順列と、前課題曲の『越天楽』と共通するものを除いて、残った 2種の下とエの分析譜図を加えたものが、次の譜例(146)です。
[譜例・146]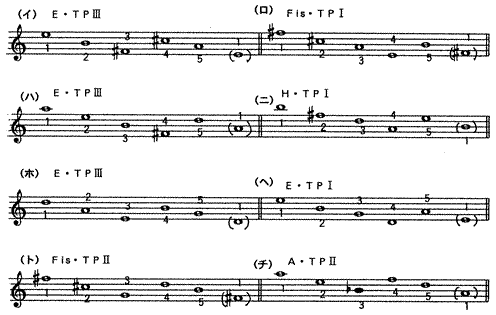
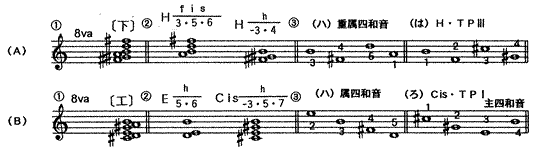
『武徳楽』に使用される合竹は、凡・下・乙・乞・一・エの6種で、下とエの2種の外 は前曲『越天楽』と共通で、その分析譜図は譜例(144)で示してありますので、こ こでは省略しますが、旋律音 g" に対応した合竹十が、『越天楽』にあって『武徳楽』にはありません。かわって前者に無くて後者に有るものが、下とエです。合竹の下は f i s に対応したものですが、この多声組織のいずれにも G i s が存在することが、前者『越天楽』とは曲調的違いを截然と図しているとも言えます。それはGに対応する十 の無いことでも、意識的相違を物語っていると言えましょう。
ところが『武徳楽』の総音域表を見ても分かるように、旋律音の中には g i s が一度たりとも出てきません。そこで下とエの2種の多声組織は、どのような和音構造から 構成されているか、当然それはA・TP � scale の重属音階上に、類推を拡大して考えることができます。
[譜例・147] 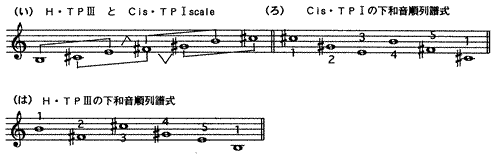
譜例(147)の(い)は、そのH・TP�と併行陽音階の Cis・TP� scale の複合音列式です。そして(ろ)と(は)、(い)の2種類の音階から解析された、下和音 順列譜式です。
これら二つの順列譜式と、譜例(146)の(A)段の、合竹下の分析譜図 の後者 分散和音は、H・TP�の主四和音の第3音( C i s )を省略し、(B)段のエ の後者は、Ci s ・TP�の主四和音にまで拡大された、多調構造であることが類推でき ます。果たして楽曲中にあって、これらの響態がどうであるかは別として、ともかく古 代楽人達の意識の中には、旋律音以外の音を合竹に用いないと言う、原楽理的不文律は、 存在してなかったことだけは、これを以て確実となった次第です。
[譜例・148]
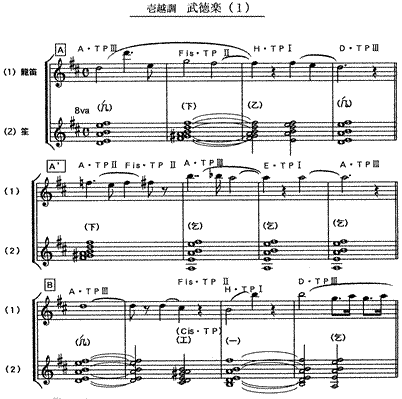
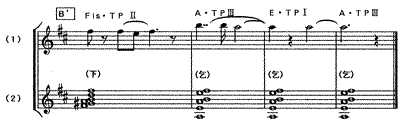
壱越調 武徳楽(1)
『武徳楽』の楽式は前曲『越天楽』と同様の、4楽節の後段2楽節の反復型です。但し 各楽句の小節数が総て倍の、拡張型4楽節となっています。
まず A 楽句の1Bは跳躍式上行二度旋律です。この合竹凡は整合です。続く2Bの 下は、fa - mi と下降した後の mi (f i s ) に対応した合竹です。従って2Bの後半2拍には、合竹内の G i s の音は、経過的一時転調と見れば適合と言う評価が与えられますが、前半2拍間の f a (g " ) に対応しては、何ともその違和感は隠しきれません。 しかも半音下降の旋律は Fi s ・TP�と言う陰音階的性格が濃厚で、これは明らかに併行多声的障害となります。この2拍間は不適合と言う、初めての最悪な評価を 与えざるを得ません。
折角合竹には十と言う合竹があるんですから、この2Bの前半は十、後半が下となっ ていれば、理想的な転調が果たせたわけです。支配的音階感覚と旋律音という、その対 象を分けたことにより起こった、進行上の齟齬、無意図的感性音楽の弱点を、浮き彫り にしていると言えましょう。それにしても後半の適合と言う響態が、何よりの救いとな り、小節全体としては適応として見逃すことは、辛うじて出来るでしょう。
これがもし前半が適合で後半が不適合だったとしたら、それこそ違和感の極みで、楽 曲進行上の不快感は、どうすることも出来ない妨げとなることは、間違い有りません。隣 接する二つの音の進行の場合、合竹は原則として後の音に対応すると言う、古代の選択 は、矢張り体験的正解だったと言えます。
続く3B後半の乙と、4Bの凡は整合です。
そして A' の1Bの3拍目までが不適合で、4拍だけが適応となって救われていま す。
続く2Bの2拍目裏の b" は、塩梅的音律の移りとしてみられ、二つの合竹乞は適合 です。さらに続く3B4BはA・TP�の曲調で通すことも出来ますが、楽節的終止感 が必要な終節部分でもありますので、旋律音の a" を軸として、その属調陽音階E・TP�から、主調のA・TP�に進んで、その解決感を合竹との複合多調併行のうちに、 強調してみました。勿論この2小節を通奏する合竹乞は、理想的整合と評価出来ます。
続いて第2楽節に移って、 B 楽句の1Bの合竹凡は整合です。そして2Bの後半の3拍に、愈々工が使用されますが、この部分の譜表の下に括弧内に示した曲調、Ci s・TP�とすれば、少々唐突の感は否めませんが、一時的転調として整合となりそうです が、続く3BがH・TP�ですので、その属調の Fi s ・TP�から進んだ方が自然です。従ってこのコーナの合竹工は、適応という評価に止まってしまいました。
続く3Bの一は、文句無しの整合です。そして4B後半の乞は、付点の g" を対象音 a"の七度音として適合です。
第2楽節後半に移って、 B' 楽句1Bの合竹下はこれもまた一時的転調と見て、適応 でしょう。そしてその後の3小節間を通奏する合竹乞は、2Bの前半を適合で、その後 半から3、4Bの終節までは、整合という評価で楽節的解決となっています。
[譜例・149」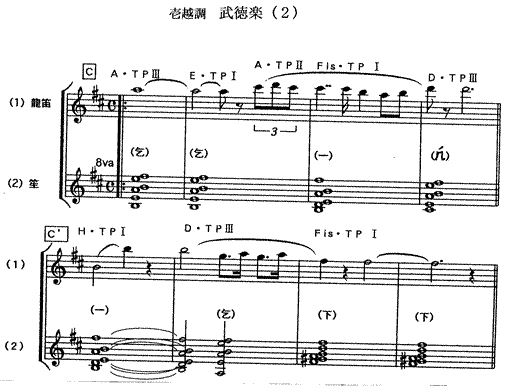
壱越調 武徳楽(2)
当課題曲後半の第2・第3楽節も前半同様の評価で検索出来ますが、注意箇所に少し く説明を加えておきます。
先ず D 楽句1Bの4拍目の f" i s 符頭上部の 十 印は、運指的技法の装飾打音のマークです。
そして曲調の推移として最も重要な部分は、 D’ 楽句の全四小節間でしょう。ここは 第4楽節の終節と同時に、楽曲の終結楽句でもあるわけです。1BのFi s ・TP�をE・TP�として、2B以下の3小節をA・TP�で持続すれば、大きな終止感を得ら れますが、楽節の終わりにレピートマークがあって、 C 楽句に戻って反覆されますので、ここで余り強い終止をしてしまうわけにもいけない側面があります。そこでこの4 小節間を、各曲調に分けて、小さいながらも完全終止進行としてみた次第です。ともあ れいづれの場合も、この2種の合竹一と凡は整合です。
結論として『武徳楽』の主調性は、所謂徴調の律、つまりA・TP�と言うことは間 違いないようです。
また予想通りこの楽曲には、旋律的古調の傾向として、曲調の体系的統一に乏しい曲 趣のものです。従って合竹下や工のように、旋律音以外の音が、それも1音のことです から、余り気にならない一時転調として、許される側面を伴っていた、とも考えられる わけです。