3.神楽歌『庭火の歌』
現在の宮内庁楽部に伝承されている古代声曲、神楽歌の全声域表を低(乙)・中・高(甲) に分けて整理して、音列式にされたものが譜例(88)です。
[譜例・88]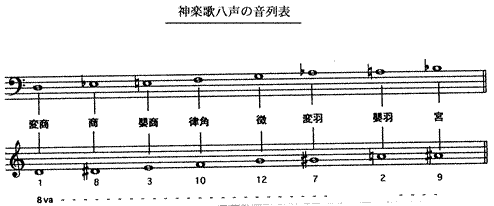
神楽歌の声域表
一つ乃至二つの複合音を更に整理して、音列式にすると、次の譜例(89)の上段で、 これをまたさらに十二律配立順に照合音列式にしたものが、下段の高音部譜表です。
[譜例・89] 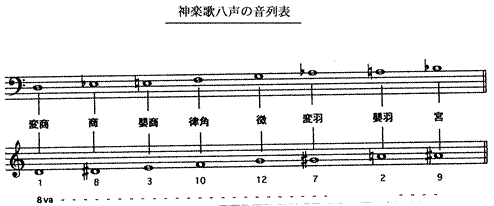
神楽歌八声の音列表
これは明らかに前記、歌曲物九声のうちの As (変徴)の一音だけを除いた、8声音列式であることがわかります。従って譜例(86)の下部に結んだ3種の呂の五音七 声の内、初めの As (変徴)調だけを除いた後の, Dis (断金)と Ais ( 鸞鏡)調の呂の五音七声の併合による8声音列式でもあります。
さて本題の『庭火の歌』は、古来和琴だけの伴奏で誦詠されて来たもので、先づ和琴 による「菅掻一段」という序奏部があり、続いて音取りのための「歌出」の手に移り、こ れが終わって歌唱部に入る形式になっています。
そして歌唱部4楽節の各中間に同様の「歌出」の手が入るが、この全段を通じて和琴 の曲調は、譜例(90)の掻き手のアルペジオで、残響音を音取りの依拠とする響態の 音組織は全く変化させることのない単一調性で一貫されています。
[譜例・90]
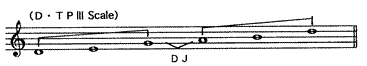
和琴の掻き手
[譜例・91]
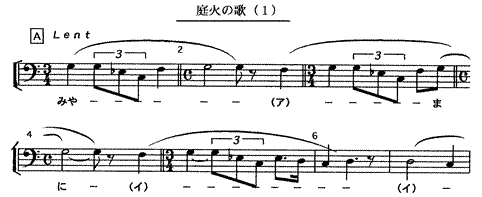
譜例(90)の和琴の調弦法から類推されるテトラ・プンクトがD・TP III scale で
(譜例、91参照)、まさにこれは壱越調律旋の音組織から構成されている、譜例(91) の曲調が意識されています。同様にこれは器楽部の曲調が、常に壱越宮が伝統的基調で あることを物語っています。
ところが歌唱部の曲調は、全くその音組織の支配を受けることなく、器楽曲調(譜例、 91)の第2核音g(律角)音だけを、共通核音として聴き取っていたのです。
[譜例・92]
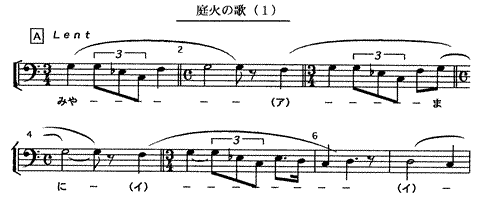
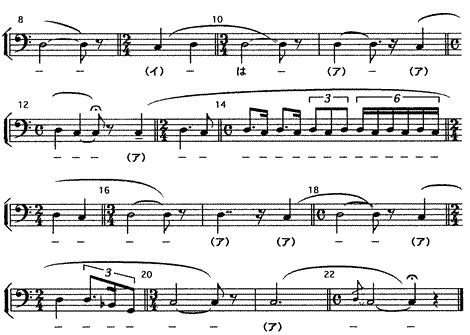
庭火の歌(1)
譜例(92)は神楽歌『庭火の歌』の歌唱楽部初頭の第一楽節です。
歌詞は「みやまには」の一節一詞で、やまにはの各音節の産み字(母音)を引き延ばす と言う、所謂歌詠形式により、4楽節で1段の楽式構成で、宮中の典型的式典歌曲様式 とも言えます。
まず第1楽節は、中音域のg(律角)から初まって、中間に es (変商)を経過して
c(嬰羽)に三連で下降し、そこから完全四度上のf(嬰商)に跳躍し、そのfを導音 として頭音のgに上行して中間解決を果たしています。これは慣例律の2音旋法の上音 解決と言う、自然音階機能が息づいています。
しかもこの上行解決の長二度音程は、1小節2拍目裏の完全四度関係とを加味すれば、 DJの接続部分に該当することが、内在されているようです。さらに確認のために旋律 を追って見てください。4小節までは全く同様の音構造のヘテロホニーで、これまでの 支配音列は間違いなくfからgの長二度音程をDJとする、譜例(87)の第4段下部 の、C・TP I scale を類推することが出来ます。
続いて5小節3拍目の付点の裏、d(宮)を経過してc(嬰羽)まで下降し、6小節 2拍目で再びdに戻って中間解決しています。ここに見られる長短二度の3連続音には、 中間音終止と言う、慣例律機能が完全に生かされています。また同時にこの3連続音は、 新たに出現した調性推判の鍵とも言えるもので、当然のことながらcからdの長二度が DJと考えられ、この楽句は明らかに譜例(87)の8段目の、G・TP � scale の曲調に、一時転調がなされていることが判明したわけです。
しかも驚いたことに、前出のC・TP � scale と言う陽旋音階と、このG・TP� scale と言う陰旋音階とは、変ホ長調(Es dur)と言う同一調号内の平行音階でもあることです。わが国の民謡の曲調を代表する二つの音階が見事に習合された近親転調 だったわけです。
そして同時に、古代声曲に入って早くもその第1曲目の前段で、東アジアの陽旋と陰 旋の音階の存在を、確認することが出来たと言ってよいでしょう。
以下の7小節目から18小節までは、所謂メリスマ的様式( melismatic style )で、断続的旋律の移行は、G・TP� scale のDJ機能の持続でもあります。
そして18小節4拍目のc(嬰羽)から19小節の頭音のd(宮)はそれまでのDJ 部分の持続させているかのように見せて、その実はG音とC音と言う二つの共通核音を 利用した転調で、完全五度音列的に下降し、持いて完全四度上に跳躍する、最初の旋律 型の移調とも見られるわけです。
さらにこの18、19小節間で出現した、b〜c〜dの各長二度の3連続音が、また 新たな調性発見の鍵となって、譜例(87)の3段の下部、G・TP�scale に転調されていると見られます。しかもこの音階は前出のG・TP II scale と、核音の総てを共通し、テトラ・プンクトの中間音だけの移動によって発生した、極めて自然転調 型でもあります。
これを複音楽とした時には、まことに味合い深い響態が得られます。
続く19、20小節に跨がる、完全四度の跳躍終止は、G(律角)を共通核音とした 転調型で、初めてのC・TPIscale に戻っています。これはそのまま洋楽理論の属音から主音と言う、ベース進行型を思わせる終止感が、見事な安定感となって、第1楽 節を解決させています。
またこの歌唱楽部の記譜法は、実音本位の無調性で採譜されていますが、変ホ長調の ソルフェージュで歌唱すれば、無理のないことも明らかになりました。
しかもこの和琴の調弦法との多調性は、g(律角)の共通性だけを意識したところから生じた、無意図的多調性だったと言えるでしょう。流石に歌中では違和感は否めず、音 取りだけの序奏部で止めたものと見るべきです。そして本来の曲の譜表は、定量リズム 形式で、2・3・4拍子の連繋で記されていますが、レントと指定された速度から考え て、その本質は1拍1小節の定量音価進行とみるべきです。
[譜例・93]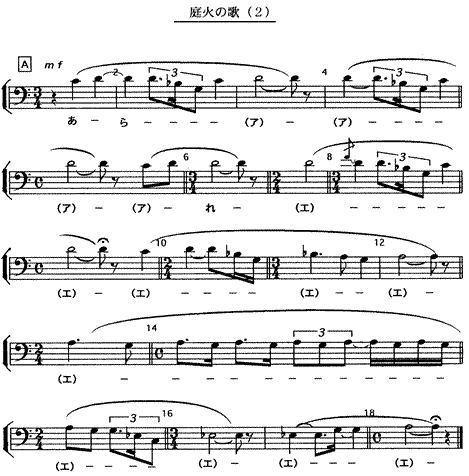
庭火の歌(2)
譜例(93)は『庭火の歌』の第2楽節で、歌詞は「あられ」という一語の名詞を、歌 詠様式で延ばした18小節です。
中音域のc’(嬰羽)から始まって、甲音域のd’(宮)に上行し、その持続音から3 連で完全五度下降し、そこから完全四度上に跳躍すると言う、第一楽節で定型となった 旋律型の移調を繰り返して、一時的解決型から始まっています。ここではB〜C〜Dと 言う長二度の3連続音列が、調性推判の新たな鍵となって、譜例(87)の3段目下部 のG・TP�scale がその支配的音階であることが判ります。
これはつまり第1楽節の解決調性の、C・TP� scale から完全五度上に、転調され
ていると見てよいわけです。そしてこの調性は6小節まで持続し、次の7小節から8小 節の1拍目の間に、あえてスモールノートとは言え、音階的には突出してe’に当てゝ d’に戻る、このD〜E〜Dは装飾的経過音ですが、G核音の陽音階が長く続き過ぎる ところから、変化を求めてE音に当てたものと見れば、調性的には無視できないものが あると見るべきでありましょう。従ってGとCとDと言う三つの共通音を利用して、7 小節目から8小節の1拍目までを、譜例(87)の1段目下部のA・TP�scale に転調して、その2拍目で再び元のG・TP�scale に戻ると大変効果的です。歌唱楽部としても高音域の楽句にも当り、一種の躍動感を強調する意識的補完も果たせます。し かもこの第2楽節の解決終音はA音ですので、響態的志向性を感じさせるためにも、三 度六度転調は遠くて近い響きとして相応しいものでしょう。
さて続く9小節目のd’の3拍ヘルマーターは、これまで2回も繰り返された一時的 解決音ですが、3度目のこゝでは、特に旋律音を強調しておいて、次の新たな調性に移 る予動とするべきでしょう。従って6・7小節とは同音でありながら調性の変化が必要 です。
従来のGから完全五度上(属音)の近親調、譜例(87)の2段下部の、D・TP� scale が最も自然です。尤もこの神楽歌の歌唱楽部は、声曲的で他に一切の音が鳴って いない単音楽ですので、調性的にはその変化には余り関係がないと思われますが、複音 楽としての将来を志向しての本講基本編ですので、一応参考までに、調性的模索の手順 を申し上げておきます。
ともあれ9小節目の4拍目から元のG・TP�scale に戻って、11小節の付点四分のあとの2拍目裏のaからgに下降するところで、短二度長二度の3連続音が出現し ます。これを新たな調性の鍵として、譜例(87)の7段目のD・TP �scake に転調していると考えられます。続く12小節目のa(徴)で、Dより完全五度上の陰旋、譜 例(87)の6段目 A・TP� scale に移調して、13小節から再びD・TP� scale に戻って、15小節の1拍目まで持続して、その裏の2拍目の長三度短三度の3連下降 の五度は、譜例(87)の8段目G・TP�scale に転調し、16、17小節と持続し、最後の18小節で元のD・TP�scale に移って解決します。
そしてこの調性解決は次の中間の和琴の歌出しのためには、比較的自然なようです。
[譜例・94] 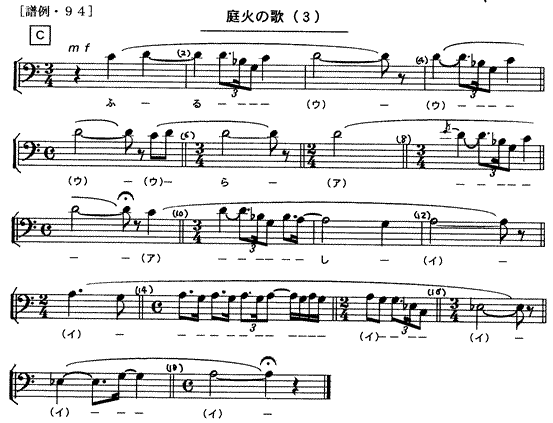
譜例(94)の第3楽節18小節は第2楽節と大同小異の曲態で、ヘテロホニー型レピートと言ってよいほどです。
従ってこれからは調性的解説は省略し、学習者諸賢はこれまでの範例に倣って、各自 で独習してみることをお勧めしておきます。
[譜例・95]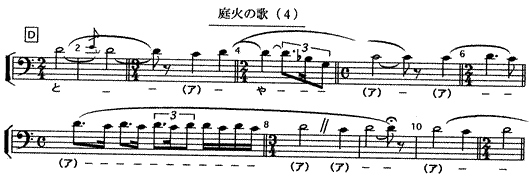
譜例(95)の第4楽節25小節は、『庭火の歌』の最終楽節です。従って完結を意識 して、第3楽節に類似した曲態ながら、ある程度の変化が必要です。例えば5小節目の 詠声の延ばしc’の持続は、従来の調性G・TP� scale でも充分に通じるわけですが、更に旋律音を強調するために、譜例(87)の4段目下部のC・TP�scale へ一時移っておいて、次の6小節目から再び元のG・TP� scale に戻った方が、より効果的でしょう。
その後はまた各自の独習に俟つこととして、最終の24・25小節について考えて見 たいと思います。
24小節がG・TP� scake 、そして25小節でD・TP� scale と言う、第2・第3楽節同様の終止形は、一応は下属音から主音に戻って終わっているかのように 見られがちですが、楽節全体の支配的曲調を見た場合、G・TP�scale で始まっているところか、第1核音としての性格はDよりGが強く、24小節のG・TP�scale は、当然同主音転調(陽から陰)と見做すことができ、従って解決音のD・TP�scale は、その属音に移った中間終止でしかあり得ないわけです。ところがペンタトニックの 場合は、その限りにあらずなのです。陰旋音階を主調とする我が国の音曲には、この様 な属音的終止が余りにも多く、お隣の韓国の宮廷様式や中国の音曲も、その殆どがこの亜流と言ってよい程で、東アジアの器楽的終止形の特質とも言えます。こうした偽装終 止こそ、東アジアのペンタトニックの完全終止だったのです。