5.漢の階音名と呂律の関係
五音七声の階名音は、その本質的分類としては、漢シラブルネームと称別するべきで しょう。そして通常シントニックコンマ(Shintonic comma)と呼ばれている微分音音 列の上に最初に確立された呂音階は、正確には呂旋音階(Romusical scale)と言うべきです。そしてこの呂旋音階を母胎として、派生し定着した律旋音階、そしてこの律旋 音階から朝鮮半島や我が国に到るまでの地域で派生し定着した陽旋そして陰旋、さらに 沖縄では固有的陰旋等々と派生し、今日まで伝えられている声曲の総ては、原則的に五 音階構成となっています。
しかしこれらの五音階声曲は所謂ヨナ抜き五音階(Pentatonic Scale)の類系と見られがちですが、スコットランドやハンガリーなどのヨナ抜き五音階とは、全く似て否な るものなのです。つまり沖縄陰旋以外のものはすべて do に核音機能がないところから、複音楽として考えた場合、全くその和声的構造が違ってきてしまうものです。机上の論理とは異なって、実際の音楽創造の現場と言う側面から、この事だけは声を大にし て申し上げておきたい事柄なのです。従って筆者はヨナ抜き五音階との混同を避けるた めに、漢律を規準とする東洋的五音階に対して、前者のペンタトニックと区別してオリ エンタル.ペンタトニック(Orientl pentatonic)と呼ぶことにしています。この称別意識は器楽構成の際の低音進行や、和音構造の本質的な違いを自覚するためのものだっ たわけです。
従って本講では、この称別法に基づいて論証を進めることに致しますので呉々もご了 承ください。
さて煩瑣な前置きはこの位にしておいて、本題に移ることにします。先ず漢の宮廷式 楽の沿革を辿れば、常にその時の支配者たちが、民族の開祖として黄帝を仰ぎ、その畏 敬の根本義礼として邸内の中心部に祖廟を設け、そこを宮所と定めていたのです。そし て常時祖霊に対する祭祀を怠ることなく、この儀式を礼節の第一におき、その祭祀奏楽 が雅楽と位置付け、奏楽典礼の根幹として、けっして他の式楽にはこの名称を用いない よう、厳格に守り続けていたことは、前述した通りです。
だからこそ十二律顕出の第一の音律は、黄帝の頭字を付した鐘の音律を選んだことに ついては、説明するまでもないと思います。
また当然のことながら、黄鐘の音律を音組織の第一核音として与えた階名音に、事の 始めとして字義の中の最も高貴な宮の意味名としたことも、雅楽の階音名の始まりとし て理想だったことは、言うまでもありません。〔次頁譜例(8)参照〕
[譜例・8]
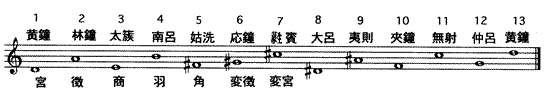
三分損益から5音7声まで
まさに名は体を現すと言う謂が、これほどに適切なものはなかったと言えます。そし て奏楽の基礎として、また旋律的音列の支配音たる主音としても、宮はそのまま不動の ものとしての願望が含まれた名称です。さらに宮には他の階音すべてのみやしろと言う、 文芸的動機まで兼備していたわけです。
こうして多様な側面からの意識を収合して、命名された宮(黄鐘)を起音として求め られた林鐘に与えられた階音名は徴です。これには澄んだとかあきらかと言った字義が あり、宮に相対する徴としての音律感を雄弁に物語っていると言えましょう。
第1段と第8段の合竹(和音)には、大変透明度が高い響態を感じた事でしょう。現 代音楽の側面から見ても、この2声音程は完全協和音程(Consonate interval)で、完全5度(Perfect 5th)に限りなく近いものである。
もとより楽理的な完全5度とか協和音的認識法や言葉すら持たなかった漢の長安では、 その音感覚を徴と言う字義で表現するよりほかは無かった訳で、まさに謂い得て妙と言 いたいところです。
次ぎにその徴(林鐘)から求められた第三の音律(太簇)には、商と言う階音名が与 えられました。この字義の第一には数学用語の割り算の答えの代名詞が浮かびます。そ の反訓として等分量、または量の測定の除して余剰なく割り切れたものと言った含意ま でに及びます。その本来は商という国名から出たものですが、この国が滅亡してからこ の国の領民達が商 に長け、諸国を行商して歩いたと言う、歴史的実態から名詞が形容 詞化して定着したものです。従って商の字義には調和とか量衡とまでに展開することが できます。
さて宮と商との音程関係を、現代音楽に置き換えて見れば、長2度(Major 2nd)となります。つまりこれは不協和音程(dissonance interval)であり、まさに不調和、不一致、不和という音程のことです。しかしながら旋律音を常に合竹の基本とする漢の長安 では、この不協和性とは全く逆転した感覚で、この長2度の転回された複合音程(compl ex interval )の9度が見えて来ます。
となると明らかにこの音律は、次ぎの安定した宮に移行するための、経過的下行導音 (leading tone)としての性格が感じられ、さらにその母胎音の徴とは完全4度(perfect 4th)でもあり音律顕出の経緯を通してみれば宮と商の不協和は商と徴と言う協和音程に 吸収され、二元性響態のなかの調和的経過と見ることができ、またその機能性が色濃く 感じられ、東洋的密集倍音(Oliental clear harmonic overtone)の真骨頂と言えるべきものです。
また商の語源を見れば、前述の行商の謂いでもあり、そこには揺動的な性格をも暗喩 しています。このように階音名としての商には、これら多様な諷意の統合として、深い 称号動機があったように思われます。
こうした多面的論証は、ともすると文芸論的瑣末重視の偏向と見られがちですが、意 識論としての視点から見れば、重要な音楽的環境の把握に通じることなのです。
続いてこの商(太簇)から求められた大呂には羽と言う階音名が与えられました。宮 と羽との音程関係は、長6度(major 6th)でこれは甲の宮からみても短3度(minor 3rd) でまさに中間的協和の習合による均衡から、6度3度の不完全協和音の成立です。
羽の字義は鳥の持つ両翼のはねであり、それはまた均勢をも意味します。さらに補佐 すると言う意味であり、確かに6度3度の協和音は終止音としての安定性には欠けてい るものの、安定協和音に移行するための経過としては最も推進力を持ったものとしての 謂いでもあるわけです。
また羽には、甲の宮に上行するためには短3度と言う音程に、多少の不自然さがある としても、調性的第2核音でもある徴に対して、下行導音としての長2度音程が理想的 で、文字通り調性を補佐する性格は強いと言えます。また商に対して完全4度を保ち、商 は宮に、羽は徴にと併行導音の均勢感こそ、羽と言う称号動機を鮮烈に浮び上がらせて います。
そしてさらに羽(大呂)から求められた姑洗には、角と言う階音名が与えられました。 角の第一義はつのです。そして角力と言う熟語によっても解るように、競うとか比べる と言う第2の含意もあるわけです。
宮と角との音程関係は長3度(major 3rd)、前出の羽に対して完全4度、商に対して長2度と言う音程関係です。従って羽から徴に、角から商に協和感を損なうことなく移行する併行完全4度、前述の併行4度ほどの調性的安定感は得られないとしても、やが て別の調性空間を意識した転調的経過としては欠くことの出来ない揺動性が横溢してい ます。
やがてこの呂の5音階の中で、角と徴、羽から甲の宮の間の短3度音程が、不自然で もあり旋律的にも跳躍的無理を感じ、この二つの音幅の間にそれぞれ変徴・変宮を設定 することにしたわけです。しかしこのような臨時記号(accidental)によつ派生音を設 定したことは、楽理的発想ではなく、律管の管列を手法的に対応させて笙に転換したと 言う、奏楽上の都合から定められたと見るべきでしょう。その証左としては呂の五音七 声のように祭祀式楽を奏する場合、好尚的価値観を必要としないことから、少しの違和 感を生じることはなかったようですが、同音階とその付加音二声の音列は、宴楽のよう な歌舞の奏楽の場合、当然その底流にある声曲的慣例律(natural musicaltone)に対しては、不自然な響態が多く、核音転位による律の五音七声へと移行していったようで す。
譜例の(8)後半の黒符頭の部分は、三分損益法で顕出した第7音までの順を追って、 五音七声を配立し、その後続けて顕出された十二律確立までの経緯を、譜表上の現代符 に置き換えてみたものですが、黄鐘調と言う調性音域から離れた遠隔音としての判別を 安易にするために符頭の色で示したものです。
そして続く譜例の(9)は十二律顕出の順位を離れ、符頭に示された白黒のみを残し たまま、音高順と言うより律管の長さの順に、整理された十二律の第1段から、第13 段迄の譜表上の音位を記したものです。
またこの下段の音名表は、我が国に伝わってからの改定され今日伝えられた名称を元 の漢音名と対照させて示したものです。
我が国に伝えられ朝廷式楽となった雅楽は、漢における同名の祭祀楽とは関係なく、当 然音名の称号動機を改めて、壱越・断金・平調・勝絶・下無・双調・鳬鐘・黄鐘・鸞鏡・ 盤渉・神仙・上無・壱越と古代としては国風の名称だったと言われていますが、筆者は 楽器類と共に我が国に渡来してきた人々の見た倭風名と考えています。
[譜例・9]
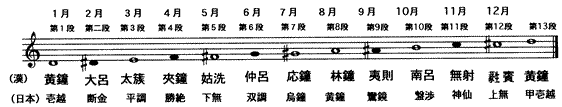
さて漢の長安では、元旦の祖廟奏楽が年間を通じて一切の行事の始まりとされ、その ために設定された音階の五音七声の主音である宮を、月ごとに1段づつ上げて、所謂1 段(半音)づつ移調していたと言われています。
譜例(9)の最上段に記された月別表は、その移調された宮の月別の位置を示したも のです。そこでその月々の位置と、符頭の白黒の状態との関係にご注意ください。
白符頭の月は1月、3月、5月、7月、8月、10月、12月に当たり、黒符頭は2 月、4月、6月、9月、11月に当たっています。
すなわち大の月に当たる処は白符頭、これは黄鐘宮の調性に関係深い近親音となって いることです。また小の月に当たる処は一つの例外なく黒符頭、つまり黄鐘調の遠隔音 に当たる事になっています。
筆者はこれまでに、太陰暦法と十二律に関する説話や、文献類に接したことがありま せん。しかし図らずも見てしまった不思議なこの整合は、ただ単に偶然とか牽強付会説 として、一蹴出来ないなにかがあるように思われてなりません。
また三分損益法の過程のうちに見えてきた、四等分、三等分の手法を按ずるにつけ、3 カ月を一単位とする季節的規準や、一年を四季に分割すると言う3と4の算定単位の定 則性とは、一体どのような関係にあるのだろうか、などとその思いは尽きるところがあ りません。
ともあれ往時は、世界で最も理知を兼備した漢民族のこと、その着想には図り知れな い高邁なる摂理が秘められていたことだけは、確かと言ってよいでしょう。一応ここで 筆者の早計を許していただくならば、あの太陰暦作制の関係者たちも加わっていたのか も知れません。勿論目下のところこれは仮説的段階です。
さて楽理的方向に思いを戻して、月毎に移調して奏楽体験を重ねるうちに、極めて大 切な進化の糸口を掴んだのです。それは8月の調性で、林鐘を宮とする音階に最も自然 に奏楽的響態と、声律に近い旋法が得られることを体験的に発見したことです。
先ずはじまりは、第8段の林鐘から宮商角と各1段置きに進み、続いて2段置いて徴、 そして1段置いて羽、さらに2段置いて甲の宮としたこれまでの手順としては、黄鐘宮 の呂の五音階と全く同じ移調だったわけですが、そのうちに角は1律上がった黄鐘(甲) に移した方が旋律的に自然な音律になることに気づき、これに律角と言う階音名を付加 し、羽と宮の間に変宮を設け、この新たな音列構造に律旋と呼んで、呂旋に対応させて 称別することにしたのです。そして宴楽の主流はこの律旋によって行われるように次第 になっていったのです。
次ぎの図の(7)は漢の長安で律管の調性的手法として示された、呂と律の音列構造 の対照法です。
〔図の7〕
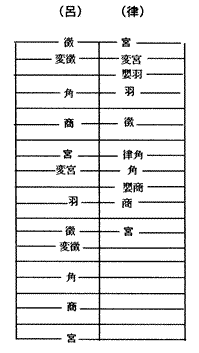
我が朝に伝えられた奏楽の基本調性はこの律旋と見られます。そしてこの音列の中間 に、角の1律下に嬰商。羽の1律上に嬰羽を付加して、雅楽朗詠の様な陰旋法へと展開
し、声楽的慣例律の定着を果たしたものと言われています。
しかし筆者は、この嬰羽.嬰商は古代朝鮮半島で付加されて、我が朝の中世のはじめ に伝えられたものではなかろうかと考えております。
続く譜例(10)は図の(7)の律管図表を、現代の譜表上に置き替えて見たものです
譜例(10)
